仕事を辞めたりして、生活が苦しいと、生活保護を受給しようか迷われると思います。
そこで気になるのが、生活保護を受給するメリット・デメリットはどういうものなのか?だと思います。
生活保護のメリットと言うと「働かなくても生活するのに必要なお金が支給される」くらいしか認識がないのではないでしょうか?
実は毎月生活費がもらえる以外にも様々なメリットがあります。
また、生活保護の申請・受給することで、調査をされたり、多少の制限が掛かるなど、当然デメリットもあります。
そこで、このページでは、生活保護を受給するメリット・デメリットについて、わかりやすく解説していきたいと思います。
生活保護を受給するメリット

まず始めに生活保護のメリットについて、ご紹介します。
生活保護を受給するメリットは全部で8つあります。
それでは一つ一つのメリットについて、それぞれわかりやすくご説明します。
多少の贅沢ができるお金が毎月支給される

生活保護の最大のメリットは、何と言っても毎月決まった日に決まった金額が支給されることです。
支給日は自治体によって異なりますが、大抵は毎月1日~5日までのいずれかの日に支給されます。

Q 生活保護費の支給日はいつ?定例支給と追加支給の支給日を紹介
生活保護の受給が開始されると、生活保護費が支給されるようになります。 では、いつ生活保護費が支給日されるのか?気になりますよね。 実は、生活保護費の支給日は、生活保護費の支給方法や支給月、福祉事務所によって変わってきます。 そこで、このペー...
支給金額についても、世帯の人数は世帯の構成員によって異なるため、一概に「毎月いくら支給される!」とは言えませんが、最も支給金額が低い単身世帯であっても、多少の贅沢ができるだけのお金が毎月支給されます。

生活保護の最低生活費は一人暮らしだといくらになる?
生活保護を申請して、受給が開始されると、最低生活費に足りない分のお金が毎月生活保護費として支給されます。 では、その生活保護費は一人暮らしだと毎月いくらもらえるのでしょうか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは、生活保護の最...

生活保護は贅沢できる?贅沢をするのは図々しいことなのか?
「生活保護は私達が払った血税から支払われているのに、その生活保護費を使って贅沢するとはどういうことだ!?」と言う声はケースワーカーとして働いていると、市民の方から、よく頂きます。 では、果たして、生活保護受給者は贅沢をしてはいけないのでしょ...
生活保護で保障されているのは「最低生活」のはずなのに、なぜ多少の贅沢ができるのでしょうか?

生活保護の最低生活費とはいくら?最低生活費の計算方法は?
よく生活保護制度の中で、「最低生活費」と言う単語を聞くと思います。 それもそのはず、生活保護の条件が「世帯の収入が最低生活費以下であること」なので、最低生活費が非常に重要な指標となります。 しかし、ケースワークの現場でも、実際によく使う言葉...
その答えは生活保護では「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されているからです。
この「健康で文化的な」がキーワードで、この文言により、生活保護では趣味や娯楽に使えるお金も支給されています。
そのため、生活保護受給者でもネットフリックスやアマゾンプライムに加入してパソコンやテレビで映画・ドラマを視聴したり、ゲームで遊ぶこともできます。

生活保護でもテレビを持てる?テレビの購入費用は出る?
生活保護を受給すると、様々な制約が掛かり、してはいけないこと、所有してはいけないものが出てきます。 では、テレビはどうなのでしょうか?生活保護の制約の対象になるのでしょうか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは、生活保護受給...

Q 生活保護者でもパソコンやゲーミングPCを持てますか?
Q 生活保護者でもパソコンやゲーミングPCを持てますか? A 生活保護者でもパソコンやゲーミングPCを持てます。 生活保護受給中はパソコンやゲーミングPCを持ってはいけないのでは?と思っている人がいますが、生活保護受給者がパソコンやゲーミン...

生活保護でゲーム機を買っても良い?ゲームを売ったら申告が必要?
生活保護の受給を開始すると様々な制限や義務が発生します。 では、果たしてゲーム機を所有・購入したり、ゲームをプレイすること等は生活保護の制限に引っかるのでしょうか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは ・生活保護受給者はゲー...
禁止されていると勘違いされがちですが、実はお酒やタバコ、パチンコ等のギャンブルをすることもできます。

Q 生活保護費でお酒を購入しても良い?
Q 生活保護費でお酒を購入しても良い? A 生活保護費でお酒を購入しても問題ありません。 生活保護受給中はお酒を買ったり、飲んだりしてはいけないのでは? と思っている人がいますが、生活保護受給者が生活保護費でお酒を 買っても飲んでも何も問題...

Q 生活保護費でタバコを購入しても良い?
Q 生活保護費でタバコを購入しても良い? A 生活保護費でタバコを購入しても問題ありません。 生活保護受給中はタバコを買ったり、吸ったりしてはいけないのでは? と思っている人がいますが、生活保護受給者が生活保護費でタバコを 買っても吸っても...

生活保護受給者はパチンコ等をしても良いの?
Q 生活保護受給者はパチンコ等をしても良いの? A 何も罰則はありません。生活保護受給者はパチンコをすることが認められています。 日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 と定められています...
海外旅行の場合は返還金の対象になりますが、旅行にだって行くことができます。

生活保護でも旅行はできる?実家への帰省もできない?
生活保護の受給を開始すると、様々な制限が掛かってきます。 例えば自動車やバイクの所有や利用は認められていませんし、就労指導を受けたり、数ヶ月に1度訪問調査を受ける必要があります。 では、旅行はどうなんでしょうか? 国内旅行や海外旅行も生活保...
このように、生活保護を受給すると、多少の贅沢ができるお金が働かなくても毎月支給され、しかも、そのお金を、ほぼ何の制限もなく自由に使えると言うメリットがあります。

生活保護の暮らしぶりは?どんな生活を送っている?
生活保護は最後のセーフティネットと呼ばれているように、様々な制度を活用したり、検討した結果、それでも生活が苦しい人が最終的に行き着く制度となっております。 生活保護で保障されている生活とは「健康で文化的な最低限度の生活」であることから、その...
子どもにしっかりとした教育を受けさせることができる

生活保護を受給するメリットとして、子どもにしっかりとした教育を受けさせることもできます。
一昔前の新聞記事で、母子世帯の生活保護受給者が取り上げられました。
その世帯は生活保護費の支給金額が少ないから、子どもを習い事や塾に通わせられないと記事の中で訴えていました。

生活保護は月額29万円も貰える?29万円以上もらっても苦しいと訴える理由
2013年3月6日に発刊された朝日新聞の朝刊の記事で生活保護受給中の母親がとりあげられました。 記事の内容としては、生活保護を受給している母子3人世帯の母親が生活が苦しいことを訴えていますが、支給金額は月額29万円もあり、生活費の内訳も被服...
しかし、実態はと言いますと、生活保護受給中でも子どもにしっかりとした教育を受けさせることはできます。
子どもが増えると、児童養育加算が付くようになりますし、生活扶助費も増額されます。

児童養育加算
児童養育加算の要件や金額等について詳しく説明しています。

生活保護の生活扶助とは?生活扶助の基準や金額についてわかりやすく解説
生活扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の1つです。8つの扶助の中でも生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものを購入するために支給される大事な扶助です。そのため、このページでは、生活扶助の基準や金額について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。
また、子どもが小学校、中学校に通学を始めると、別途教育扶助が支給されるようになります。

教育扶助とは?教育扶助の基準・金額・対象についてわかりやすく解説
教育扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。教育扶助では義務教育(小学校・中学校)にかかる給食費や教材代、交通費、部活動にかかる費用等、あらゆる費用が支給されます。このページでは、教育扶助で基準や金額、支給される項目等について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。
高校生になると、教育扶助はなくなりますが、代わりに生業扶助が支給されるようになります。

生活保護の生業扶助とは?高校進学や資格取得等の自立に向けた費用が支給される
生業扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。生業扶助では高校の学費や資格取得費など世帯の収入増加、又は自立を助長する上で必要な費用が支給されます。このページでは生業扶助で支給される項目について、わかりやすく説明しています。
生活保護では高校卒業後は就職して働くことが想定されているため、残念ながら、大学や専門学校の学費までは支給されません。

生活保護でも大学・専門学校に進学できる?学費や生活費はどうなる?
一昔前までは、高校を卒業して、すぐに働く人が多かったですが、最近は、大学・専門学校に進学する人が増えてきています。 そのため、 「友達と一緒に大学・専門学校に進学して、もっと多くのことを学びたい!」 「子どもは大学・専門学校まで行かせてあげ...

学生の一人暮らしでも生活保護は受けられる?若者は受給できない?
全ての国民が生活保護を受給する資格を持っていますが、果たして大学生や専門学校等に通っている学生の一人暮らしでも生活保護を受給することはできるのでしょうか? また、生活保護を受給できない場合は、なぜ生活保護を受給できないのでしょうか?学生だか...
しかし、高校卒業までは、これら教育扶助・生業扶助が支給されることにより、教材代や給食費、通学のための交通費、入学準備金、部活動に掛かる費用等、様々な教育に必要な費用が支給されます。

生活保護費から小学校、中学校、高校の入学準備金は支給される
小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒がいる生活保護世帯の親御さんは子どもの制服代等をどう工面すれば良いのか?不安を抱えているのではないでしょうか? 安心してください。 生活保護受給中の世帯に小学校、中学校、高校に入学する児童、生徒がいる...

Q 生活保護受給中でも部活動をすることはできる?費用は生活保護費から出る?
Q 生活保護受給中でも部活動をすることはできる?費用は生活保護費から出る? A 部活動はできます。実は毎月の支給金額にも部活動費が含まれています。 日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 ...
特にシングルマザー、シングルファザーと呼ばれる母子家庭・父子家庭の場合、子どもが病気等をした場合に仕事を休まなければいけないため、正社員やフルタイムで働くことは難しく、生活が非常に苦しいと思います。
しかし、生活保護を受給すると、母子家庭・父子家庭の場合は、母子加算も付くことから、普通に働くよりも遥かに多くのお金を得ることができるため、子どもの教育に力を入れる余裕もできます。

母子加算
生活保護受給中の世帯がひとり親家庭の場合、母子加算が支給されます。名称は母子加算ですが、父子家庭でも母子加算はつきます。このページでは母子加算の要件や金額等について詳しく説明します。

母子家庭の生活保護費はいくら?働くよりも贅沢な暮らしができる?
「母子家庭の生活保護受給者はずるい!生活保護費をもらいすぎている!」等の声をよく聞きますが、実際に母子家庭だと生活保護費はいくらもらえるのでしょうか?パート・アルバイトで働くよりも生活保護をもらった方が贅沢な暮らしができるのでしょうか? ま...
このように、働きながら子育てをするのは非常に大変ですが、生活保護を受給することで、時間的にも金銭的にも余裕ができ、子どもにしっかりとした教育を受けさせることができると言うメリットがあります。
子どもを優先的に保育園に入園させることができる

生活保護のメリットとして、子どもを優先的に保育園に入園させることができます。

Q 保育園に通わせることはできますか?
Q 保育園に通わせることはできますか? A 保育園に通わせることはできます。ただしケースワーカーによる就労指導が厳しくなります。 保育園に通わせることは生活保護受給者の自由のため 通わせたいのであれば、通わせることはできます。 ただし保育園...
現在働いていなくても、また、病気等で働ける状態になかったり、そもそも働く気が一切ない場合であっても関係なく、生活保護を受給していると言うだけで、優先的に保育園に入園させることができます。
もちろん、保育料は無料です。
働いている人よりも生活保護受給者を優先するとは何事だ!と言うクレームを市民の方から受けることもありますが、生活保護受給者を優先する理由は、生活保護を早く脱却してもらえるように、まずは働く環境を整えるためです。
当然、保育園に入園させた以上は治療に専念したり、就職活動を積極的にしなければいけないため、ケースワーカーによる指導も厳しくはなりますが、このように、生活保護を受給すると、子どもを優先的に保育園に入園させることができます。

ケースワーカーとは?仕事内容は?
生活保護受給者には、必ずケースワーカー(CW)と言う担当の人がつきますが、このケースワーカーとは、そもそも何者なのか?どういう仕事をするのか?よくわからないと思います。 そこで、このページでは ケースワーカーはどうい人なのか? 仕事内容は?...
ちなみに幼稚園にも入園させることができますが、幼稚園の方が自己負担額が多いため、保育園に入園させる方がメリットがあります。

Q 幼稚園に通わせることはできますか?
Q 幼稚園に通わせることはできますか? A 幼稚園に通わせることはできますが、保育料は出ません。 幼稚園に通わせることは生活保護受給者の自由のため 通わせたいのであれば、通わせることはできます。 ただし幼稚園は義務教育ではありません。 その...
無料であらゆる医療行為を受けられる

生活保護のメリットとして、あらゆる医療行為を無料で受けることができます。
生活保護を受給すると、医療扶助が支給されるようになります。

生活保護の医療扶助とは?現物給付によりタダで病院で治療を受けられる
医療扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。治療に必要なあらゆる医療が医療扶助により、タダで受けることができます(現物支給)。ただし、自己負担が発生する場合などの注意点もあるため、このページでは、医療扶助の内容・制限等について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。
この医療扶助により、国民健康保険の保険給付の対象となるサービスは全て無料で受けることができます。
例えばガンになった場合、入院して抗がん剤による薬物療法やガンの摘出手術をしますが、それらも全て無料で受けられます。

生活保護受給中に入院した場合の注意点
生活保護受給者が入院すると生活に様々な影響が出ます。 良い影響ならいいのですが、残念ながら悪い影響が出ます。 そのため、入院する時の注意点をまとめました。 注意しないと、生活に支障が出るので、入院予定の方は、 必ず目を通してください。 ケー...

生活保護のがん治療はどこまで?投薬は?手術は?先進医療まで受けられる?
生活保護を受給すると、病気になった場合の治療費や薬代は医療扶助から支給されます。 では、もしも生活保護受給者ががんになった場合やがんになったことで仕事ができなくなり、生活保護の受給を開始した場合、どこまで医療扶助では、がん治療ができるのでし...
残念ながら、放射線治療の「陽子線治療」や「重粒子線治療」の他、「内視鏡手術支援ロボット(ダビンチ)」による患部の切除手術など、いわゆる先進医療は、国民健康保険のサービス対象外のため、医療扶助は支給されません。
とは言え、先進医療と言えば聞こえは良いですが、先進医療とは要するに国がまだ認可していない危険な医療行為であり、非常にリスクの高い治療法であるため、受けられなくても、特に支障はありません。
注意点として、病院を初めて受診する場合は、医療券を発行してもらう必要がありますが、そのひと手間だけすれば、後は継続して医療扶助を受けることができます。

生活保護受給者が病院を受診する場合の流れや手続き方法について
生活保護の受給が開始すると、8つの扶助を受けることができます。 この8つの扶助のうち、医療扶助を利用することで、生活保護受給者は無料で病院を受診することができますが、それには福祉事務所で手続きをする必要があります。 そこで、このページでは、...

生活保護受給者が医療券なしで受診する方法
生活保護を受給すると8つの扶助を受けることができます。 その8つの扶助の中に医療扶助があり、この医療扶助を利用することで、生活保護受給者は診察代、薬代、手術代等、医療に関するあらゆるサービスを無料で受けることができます。 この医療扶助を受け...
「生活保護を受けたくない!」と思っている方も入院中は働けないことから、病気が治るまでの間だけ生活保護を受給し、治療完了後に生活保護を辞めると言う方もいます。

生活保護をやめたい時の辞め方や辞退届の出し方について
生活保護の受給を開始したものの、途中で生活保護をやめたい!と思った場合に、生活保護をやめることは自由にできるのでしょうか?また、一度生活保護の辞退をしたら、もう二度と生活保護の受給をすることはできないのでしょうか?気になるところだと思います...
このように、生活保護を受給すると、医療扶助により、あらゆる医療行為を無料で受けることができると言うメリットがあります。
各種支払いが免除・減免される

生活保護のメリットとして、各種支払いが免除・減免されるようになります。

生活保護だと無料になるものや支払いが免除になるもの一覧
皆さんご存知のように生活保護の受給が開始すると、毎月最低生活費として、生活保護費が支給されるようになります。 また、生活保護の受給が開始すると、お金がもらえるだけでなく、実は無料になるものや支払いが免除されるものが多数あります。 そこで、こ...
生活保護を所管とする福祉事務所は市役所内にあるため、生活保護が受給中であると言う情報が共有され、国民健康保険料や国民年金保険料、住民税、固定資産税、上下水道の使用料等の支払いが免除・減免されます。

生活保護になると健康保険証や国民健康保険はどうなる?
日本では国民皆保険制度と言うものがあり、すべての国民が公的医療保険に加入することになっており、会社勤めをしている方は健康保険に加入し、自営業の方や退職をして年金生活をしている方等は国民健康保険に加入しています。 この健康保険又は国民健康保険...
過去に滞納した税金も3年間生活保護を受給し続けることで、回収不可と見なされ消滅します。

生活保護受給者の税金は免除される?滞納分の取り扱いは?申請は必要?
生活保護の受給が開始すると税金はどうるなのか?毎月支給される生活保護費から支出しなければいけないのか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは、 ・生活保護受給者の各種税金はどうなるのか?免除されるのか? ・生活保護受給開始前に...
その他にも、生活保護を受給すると、NHKの放送受診料も免除になります。
ただし、注意点として、免除申請をしないといけません。
福祉事務所の窓口に「放送受診料免除申請書(全額免除)」と「受信料免除専用の封筒」があるので、忘れずに手続きをしましょう。

生活保護受給者はNHK受信料が免除される!ただし免除申請が必要
生活保護受給中はNHK受信料が免除されます。手続き方法や免除内容について詳しく説明しています。
なお、免除されると勘違いされる方が多いですが、残念ながら電気、ガス等の光熱費については、免除や減免の対象とはなりません。

生活保護の電気代等の光熱費は無料になったり減免の対象になる?
生活保護の受給が開始されると、様々なものが無料になったり、減免の対象となったりします。 では、どういうものが生活保護になると無料・減免になるのでしょうか? いわゆるライフラインと言われる電気・ガス・水道はすべて無料・減免の対象になるのでしょ...
このように、生活保護を受給すると、各種支払いが免除・減免されると言うメリットがあります。
就職や仕事に役立つ資格や技能を無料で取得できる

生活保護のメリットとして、就職や仕事に役に立つ資格や技能を無料で取得することができます。
生活保護には8つの扶助があり、そのうちの生業扶助では、高校生の学費等の他に、就職するために必要な費用が支出されます。

生活保護の8つの扶助とは?特性・要件・支給内容について解説
生活保護には全部で8つの扶助があります。生活保護の支給はどれも必ず、この8つの扶助のどれかに該当します。ただし、自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要です。このページではそれぞれの特性・要件・内容・支給金額等についてわかりやすく解説しています。

生活保護の生業扶助とは?高校進学や資格取得等の自立に向けた費用が支給される
生業扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。生業扶助では高校の学費や資格取得費など世帯の収入増加、又は自立を助長する上で必要な費用が支給されます。このページでは生業扶助で支給される項目について、わかりやすく説明しています。
その生業扶助の支給項目の中に技能習得費があり、これを活用することで、資格取得や技能習得に掛かる実額費用全額が生活保護費から支給されます。

資格取得費
生活保護受給者が就職するために必要とする資格取得・技能習得費用については、 資格取得費が臨時的に支給されます。 正式名称は技能習得費です。 しかし、技能習得よりも資格取得に利用されることが多いため このページでは資格取得費として説明します。...
具体的には、フォークリフト、訪問介護員2級養成研修課程修了(旧ホームヘルパー2級)、美容師の資格等の資格を取得することができます。
原則は1つの資格につき年間最大81,000円支給されますが、例外もあります。
自立支援プログラムに基づく場合で1年間のうちに複数の資格を習得する必要がある場合は1年間で最大216,000円まで支給されます。
また自立助長に資することが確実に見込まれる場合は上限380,000円まで支給されます。
この例外を利用することで自動車運転免許の取得も可能です。

Q 車の運転免許を取得できますか?
Q 車の運転免許を取得できますか? A 条件は難しいですが担当ケースワーカーに就労が確実と認めさせれば支給されます。 生活保護受給中の場合、原則として自動車を運転することはもちろん、保有することも 禁止されています。 しかし自動車のページに...
このように、生活保護を受給すると、就職や仕事に役立つ資格や技能を無料で取得でき、例外を活用することで、自動車運転免許まで取得できると言うメリットがあります。
就職してもしばらくは働きながら生活保護を受給できる

生活保護のメリットとして、就職しても、しばらくは働きながら生活保護を受給することができます。
働き始めたら生活保護を辞めなくてはいけないと勘違いされている方が多いですが、生活保護は働きながらでも受給することができます。

生活保護は働きながらでも受給できるの?仕事で得た収入の取り扱いは?
「生活保護を受けながら仕事はできない!」 「生活保護受給中は働いたら駄目!」 「働きだしたら生活保護がすぐに廃止させられる!」 と言ったデマを時々信じている方がいらっしゃいますが、それらはハッキリ言って嘘です。 生活保護を受けながら仕事はで...
生活保護の条件である最低生活費以上の収入を得るようになった場合は、生活保護の要件を満たさなくなるため、生活保護は廃止になりますが、最低生活費以下の収入であれば生活保護を受給し続けることができます。

生活保護の条件はたった1つ!
生活保護は最後のセーフティネットと呼ばれており、 生活に困窮された人のための、最後の救済措置です。 生活保護とは 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を...
例えば最低生活費が10万円の場合、働いて63,000円の給料収入を得るようになったとしても、まだ最低生活費以下のため、生活保護を受給し続けることができます。
もちろん、給料がある分、生活保護費は減額されますが、給料分全額が減額されるわけではありません。
生活保護受給中に給料収入を得た場合、基礎控除等があるため、この基礎控除分、働いた方が月々に使えるお金が増えるメリットがあります。

生活保護における給料収入の取り扱いは?収入申告しないとどうなる?
生活保護受給中に給与収入を得た場合の取扱いについて詳しく説明しています。
例えば先程と同様に最低生活費が10万円、給料収入が63,000円の場合、基礎控除額は20,000円になるため
最低生活費10万円-(給料収入63,000円-基礎控除20,000円)=57,000円
支給額57,000円+給与収入63,000円=12万円
となり、月に使えるお金が20,000円増えます。
このように、生活保護を受給すると、働いて足りない分を生活保護費として受給することができますし、給料収入が増えれば、増えるほど、基礎控除も増えるため、より毎月の生活が豊かになると言うメリットがあります。

生活保護を受けながらいくらまで働ける?稼げる収入の目安はいくら?
仕事をしていると生活保護を受給することができない、とよく勘違いされていますが、生活保護を受けながら仕事をすることはできます。 しかし、そこで問題になるのが、いくらまでなら生活保護を受給しながら働くことができるのか?と言う点だと思います。 そ...
生活保護を受給するデメリット

次に生活保護のデメリットについて、ご紹介します。
生活保護を受給するデメリットは全部で6つあります。
それでは一つ一つのデメリットについて、それぞれわかりやすくご説明します。
定期的にケースワーカーが訪問調査にやってくる

生活保護のデメリットとして、数ヶ月に1度、定期的にケースワーカーが訪問調査にやってきて、最近の生活状況等の聞き取りがあります。

訪問調査
生活保護を申請すると訪問調査が行われます。 調査内容について詳しく説明しています。
訪問頻度は世帯の格付けによって決まり、生活保護を受給したばかりの時は毎月のように訪問調査があり、生活状況が安定してきたと判断されれば訪問頻度が少なくなり、3ヶ月に1度の訪問になります。
老人ホームに入居したり、長期入院している場合でも半年に1回、もしくは1年に1回は訪問調査があります。

生活保護の老後は?老人ホームに入居できる?年金があっても受給できる?
若い時はバリバリ働いていても年を取って働けなくなり、生活保護の検討をはじめる人。 病気等を理由に若い時から生活保護を受給し、そのまま老後を迎える人。 様々な方がいますが、生活保護の老後はどうなるのか?気になるところだと思います。 そこで、こ...
訪問調査の内容ですが、就職活動の状況や通院状況、子どもの通学状況、生活環境に変化がないかを確認されます。
中には、居住実態がない場合や世帯員が増減している場合、認知症が発症している場合、子どもが虐待を受けている場合もあるため、ケースワーカーが家の中に入って家財等、家の中の状態をチェックされます。
なお、訪問調査をする場合には、事前連絡をすると意味がないため、何の連絡もなくケースワーカーが、ある日、突然家にやって来ます。
しかも、ケースワーカーは危険な仕事のため、必ず2人組で来ますし、女性職員が少ないため、特に若い女性は訪問調査を嫌がります。
このように、生活保護を受給すると、ケースワーカーが突然やって来て、家の中の様子を確認されたり、近況について根掘り葉掘り聞かれると言うデメリットがあります。
扶養義務調査で親族にバレる

生活保護のデメリットとして、生活保護を申請すると扶養義務調査をされるため、親族に生活保護を受給しようとしていることがバレます。

扶養義務調査
生活保護を申請すると親族等に対して扶養義務調査が行われます。調査内容について詳しく説明しています。

生活保護の扶養照会とは?断り方や支援する場合はどうすれば良い?
生活保護の申請をすると、各種調査が実施されます。 その調査の中に扶養義務調査と言うものがあり、生活保護の申請者の親族に対して扶養照会が送られます。 扶養照会を送られる親族からすると、ある日突然行政から「扶養できませんか?」と書類が来るわけで...

生活保護は申請すれば、ほぼ確定?受けるにはどうすべき?
毎日の生活が苦しい生活困窮者の方は、日々の生活に一生懸命で暮らしに余裕がありません。 生活保護を受給することができれば、生活は安定しますが、受給条件を満たすのか不安があると思いますし、窓口で生活保護を申請しても調査期間があるため、すぐには受...
民法第877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められています。
また、生活保護法第4条第2項に「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と定められています。
これらの法律を根拠に福祉事務所は生活保護の申請があった場合に、生活保護申請者の親族等に対して扶養義務調査を行います。
扶養義務調査の対象者ですが、絶対的扶養義務者と呼ばれる直系血族及び2親等以内の親族(祖父、祖母、両親、兄弟姉妹、子、孫等)には必ず扶養義務調査が行きます。
扶養義務調査をする目的は、親族等が申請者に対して経済的、精神的に援助できるかどうか把握するためです。
経済的援助とはお金や食料等の仕送りのことです。
精神的援助とは見守りや各種手続きの保証人や代理人になることです。
「経済的援助は、まず受けられないから扶養義務調査は辞めるべきではないか?」と言う声が多いですが、もちろん、福祉事務所も経済的援助を期待してはいません。
しかし、精神的援助は絶対に必要です。
勘違いされている方が多いですが、ケースワーカーは各種手続きの保証人や代理人にはなれません。
例えば入院が必要な場合であっても、家族の援助がなければ入院もできませんし、入院期間中の電気・ガス等を止めることもできません。
そのため、DVや虐待等により、住民票の写し等の交付等を制限しているなど、特別な事情がある場合は扶養義務調査はしませんが、「親に生活保護を申請したことがバレたら怒られる」と言った理由では、扶養義務調査を拒否することはできません。
このように、生活保護を受給すると、扶養義務調査により、親・兄弟等の親族に生活保護を申請していることが知られてしまうと言うデメリットがあります。

生活保護は親がいても受給できる?親が健在の場合の受給方法は?
日本は憲法によって健康で文化的な最低限度の生活が保障されています。 そのため、生活が苦しくて、今日の食事もままならないような状況に陥った場合等、受給条件を満たせば生活保護を受給することができます。 しかし、民法において親は子どもを養育する義...
自動車やバイクに乗れない等の制限がある

生活保護のデメリットとして、自動車やバイクの所有・運転ができなくなる等の制限が掛かります。

生活保護の自動車の取り扱いは?自動車は処分しなければいけない?
生活保護受給者が自動車を所有している場合の取扱いについて詳しく説明しています。

生活保護のバイクの取り扱いは?バイクを処分しなければいけない?
バイクを所有している方が生活保護を申請しようとする場合、バイクの取り扱いはどうなるのか? 所有・利用できるのか?処分しなければいけないのか? また、生活保護受給中の方が買い物や通院のためにバイクを購入することは可能なのか? 気になるところだ...
都会だと電車やバス等の公共交通機関が充実しているため、大した問題ではありませんが、田舎の場合、公共交通機関が発展しておらず、自動車やバイクがないと買い物に行くのも大変であったりと意外と死活問題だったりします。
では、なぜ自動車やバイクの所有や運転が認められないのか?
理由はシンプルで自動車やバイクの維持費にお金が掛かることと、事故を起こした場合に相手方に十分な保障をすることができないからです。
自動車やバイクを所有すると、駐車場代、ガソリン代、自動車税、保険代、車検代など様々な維持費が掛かります。
生活保護費だけで、それらの経費を賄うことは不可能です。
また、生活保護受給中の方で指導指示を無視して自動車やバイクに乗っている人がいますが、そういう方々は維持費を抑えるために、大抵は任意保険に加入していません。
そのため、事故を起こして相手方が怪我等をした場合に治療費や慰謝料等支払うことができません。
任意保険に加入していないことで、生活保護受給者が困るなら自業自得ですが、実際は事故で怪我させられた方が治療費や慰謝料等を請求することができず、泣き寝入りするしかないため、生活保護受給者の自動車やバイクの運転を固く禁止しています。
ただし、旅行先でレンタカーに乗るくらいはグレーではありますが可能です。

生活保護でも旅行はできる?実家への帰省もできない?
生活保護の受給を開始すると、様々な制限が掛かってきます。 例えば自動車やバイクの所有や利用は認められていませんし、就労指導を受けたり、数ヶ月に1度訪問調査を受ける必要があります。 では、旅行はどうなんでしょうか? 国内旅行や海外旅行も生活保...

生活保護でもレンタカーは借りられる?カーリースやサブスクはできる?
移動する際、特に田舎の場合は電車やバスなどの公共交通機関が都会のように充実していないことから自動車が必要になることがあります。 では、果たして生活保護受給中の場合は自動車を利用することはできるのでしょうか?気になるところだと思います。 そこ...
その他にも生活保護を受けると様々な制限が掛かります。

生活保護受給者がしてはいけないことは?罰則などはある?
生活保護の受給を開始すると、様々な制限や義務が発生します。 例えば ・所有してはいけないものがある ・収入申告書を提出しなければいけない ・ケースワーカーによる訪問調査数ヶ月に1回ある などなど、多数あります。 一度にすべてを説明することは...
このように、生活保護を受給すると、自動車やバイクの所有・使用ができない他、様々な制限が掛かると言うデメリットがあります。
福祉事務所に対して報告義務がある

生活保護のデメリットとして、何かしらの変化があった場合は、福祉事務所に対して逐一報告する義務があります。
福祉事務所には調査権限があるため、いちいち報告をしなくても、調べることができます。
だからと言って、生活保護受給者が生活の変化について報告をしなくて良いわけではありません。
もしも報告を怠り、福祉事務所の調査によって判明した場合、最悪の場合、不正受給と見なされ徴収金として、生活保護費を返さなくてはいけなくなってしまうこともあります。

Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは?
Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは? A 不正受給した金額を一括返還する必要があります。また悪質な場合は刑事告訴される場合があります。 不正受給が発覚した場合、担当ケースワーカーは収入調査・金融機関調査等の各種調査を行い まずは不正受給の...

生活保護法第63条返還金と第78条徴収金の違いとは?
福祉事務所は本来支給する金額よりも多くの生活保護費を支給してしまった場合に、 生活保護法第63条返還金又は生活保護法第78条徴収金を根拠に 生活保護者から返還又は徴収することができます。 返還金も徴収金も生活保護受給者から生活保護費を返しも...
このように、生活保護を受給すると、生活の変化等が少しでもあれば面倒でもケースワーカーを通して福祉事務所に報告する義務があると言うデメリットがあります。
ケースワーカーの指導指示には従わないといけない

生活保護のデメリットとして、ケースワーカーの指導指示には、必ず従わなければいけません。

Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?
Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか? A 最悪の場合、生活保護の停止又は廃止になります。 生活保護法第二十七条を根拠に担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、 生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指...
生活保護の受給が開始されると、担当ケースワーカーが付きます。

ケースワーカーとは?仕事内容は?
生活保護受給者には、必ずケースワーカー(CW)と言う担当の人がつきますが、このケースワーカーとは、そもそも何者なのか?どういう仕事をするのか?よくわからないと思います。 そこで、このページでは ケースワーカーはどうい人なのか? 仕事内容は?...
この担当ケースワーカーが生活保護受給者の相談に応じたり、各種調査を行い、生活指導、通院指導、就労指導など、生活保護受給者が精神的にも経済的にも自立できるようにサポートを行います。
生活保護受給者自身も生活保護を受ける以上は、治療に専念する、就職活動を行うなど、様々な義務を負うため、ケースワーカーから受けた様々な指示には必ず従わなければいけません。
そして、もしも、ケースワーカーからの指示に従わなければ、最悪の場合、生活保護を廃止されてしまいます。

Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?
Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの? A どれも月々の生活保護費の支給はありませんが全く違います。 毎月1日の生活保護費の支給がないところは共通していますが 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」で...
1度や2度、指導指示に従わないくらいで「すぐに生活保護廃止!」とはなりませんが、数回の口頭指導の後に文書で指導指示を受けたら要注意です。

生活保護が打ち切りになる条件とは?打ち切り後に再申請できる?
生活保護受給中でも、ある日突然、生活保護費の支給がとまる「打ち切り」になることがあります。 別途、収入や貯金等の資産があれば、突然、生活保護の支給がとまっても、すぐに生活に困ることはありませんが、生活保護費しかない場合は、打ち切られると、生...
文書で記載された指導内容を期限までに実施しなければ問答無用で職権により生活保護が廃止されてしまいます。
このように、生活保護を受給すると、ケースワーカーから受ける様々な指導指示に従わなければいけないと言うデメリットがあります。
国の都合で減額され生活できなくなる可能性がある

生活保護のデメリットとして、財政状況等、国の都合によって、急遽、生活保護の支給金額等が減額され、生活が苦しくなる可能性があります。
基本的には憲法で守られていますが、財政状況等によっては、生活保護費の支給金額が減額され、生活が苦しくなる可能性があります。
世界情勢を見たら分かる通り、現在、日本の主要産業である自動車は窮地に陥っていますし、今後世界の中心となるであろう産業分野のICT関連では、かなり遅れを取っています。
経済状況が悪化すれば失業者も必然的に増えますし、労働者の給料も下げられます。
そんな中、生活保護受給者だけ、今の生活水準を維持できるわけがありません。
世論によって、必ず生活保護費の減額も声高に叫ばれるようになり、その結果、実際に生活保護費が減額される危険性があります。
最悪の場合、生活保護制度そのものが破綻してしまう可能性だってあります。
このように、生活保護に頼りきってしまうと、生活保護の支給金額が減額された場合や制度そのものが破綻してしまった場合に、為す術がなく、国の動向に振り回されてしまうと言うデメリットがあります。
まとめ

生活保護のメリット・デメリットについて、できるだけわかりやすくご説明させていただきました。
生活保護を申請しようかどうか迷っている方は、上記のメリット・デメリットを参考に、どうするべきか判断していただけたらと思います。
そして、生活保護を申請すると決めた方は、下記ページにて、申請方法等についてまとめているので、ぜひご参考にしてみて下さい。

生活保護の申請から決定・却下までの流れ・必要書類・申請時の注意点
生活保護を受給したいと思うけど、
・どこに申請したら良いの?
・申請に必要なものは?
・申請してから、お金がもらえるまで、どれくらいかかるの?
等、気になりますよね?
それらの疑問に、このページではズバリお答えします。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/



























































































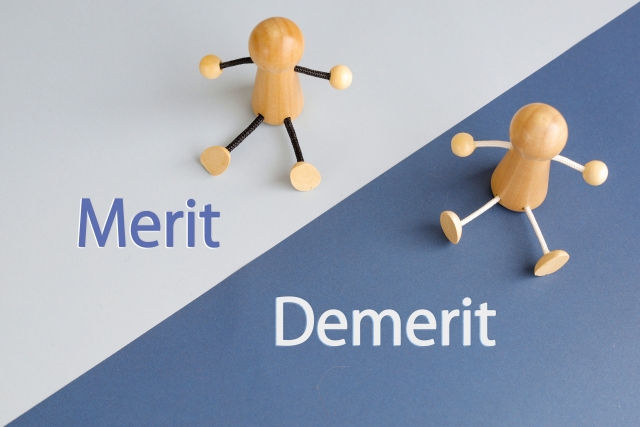


コメント