「生活が苦しくて福祉事務所に相談したいけど、どうすればいいの?」「生活保護の申請って難しそう…」そんな不安を抱えている方に向けて、この記事では福祉事務所での生活保護申請について、相談から受給までの流れを初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。
2024年の生活保護申請件数は約25万6千件で過去12年間で最多となっており、生活保護は決して特別なものではありません。
現在、全国で約200万人が生活保護を受給しています。
この記事を読めば、福祉事務所での相談方法、必要な書類、申請の流れ、そして受給までの期間がすべてわかります。

福祉事務所とは?生活保護における役割

福祉事務所の基本
福祉事務所は、社会福祉法に基づいて設置される社会福祉行政機関で、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定められた支援や事務手続きを主な業務として行っています。
福祉事務所の主な業務
- 生活保護の相談・申請受付
- 生活保護受給者の支援・指導
- 児童福祉サービスの提供
- 母子・父子家庭への支援
- 高齢者・障害者の福祉相談
全国の設置状況
市部では市が福祉事務所の設置を義務付けられており、人口の少ない地方の町村では、都道府県が各町村の業務をまとめて担当する福祉事務所を設置して対応しています。
設置の区分
- 市部: 各市が独自に設置(設置義務あり)
- 町村部: 都道府県が設置(一部の町村は独自設置)
- 特別区: 各区が設置(東京23区など)
あなたの地域の福祉事務所を探す方法
探し方
- 「お住まいの市区町村名 + 福祉事務所」で検索
- 市役所・区役所の受付で「生活保護担当課」を尋ねる
- 厚生労働省のウェブサイトにある福祉事務所一覧を確認する
呼び方の違いに注意
- 東京都: 「生活福祉課」
- 大阪市: 「保健福祉センター生活保護業務担当課」
- 横浜市: 「保健福祉センター生活保護課」
自治体によって名称が異なりますが、機能は同じです。
生活保護の基礎知識|制度の仕組みと受給条件

生活保護制度とは
生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。
これは日本国憲法第25条で保障された国民の権利であり、生活保護の申請は国民の権利です。
最新の受給状況(2024年データ)
全国の受給状況
- 受給者数: 約200万人(2025年2月に200万人を下回る)
- 受給世帯数: 約165万世帯
- 申請件数: 25万5,897件(5年連続増加、現行調査手法で最多)
- 保護率: 約1.62%(人口100人あたり1.62人)
受給世帯の内訳
- 高齢者世帯: 90万世帯超(全体の約55%)
- 傷病・障害者世帯: 約25%
- 母子世帯: 約5%
- その他世帯: 約15%
生活保護を受けられる4つの条件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

条件1: 資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる必要があります。
ただし例外があります。
- 居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります
- 自動車・バイクは原則として処分する必要がありますが、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります



条件2: 能力の活用
働ける能力がある場合は、能力に応じて働くことが求められます。

ただし、病気や高齢、障害などで働けない場合は免除されます。
条件3: 他の制度の活用
年金、各種手当など、他の制度で受けられるものはすべて申請します。

条件4: 扶養義務者からの援助
扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。


福祉事務所での相談から申請までの完全ガイド

ステップ1: 事前準備
持参すると良いもの
生活保護の申請時の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)の提出を求められることがあります。
持参推奨リスト
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳(全ての銀行口座)
- 給与明細(直近3ヶ月分)
- 年金手帳・年金証書
- 健康保険証
- 賃貸借契約書
- 光熱費の請求書・領収書
- 医療費の領収書
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- 印鑑
重要なポイント: 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。書類が揃っていないことを理由に申請を諦める必要はありません。
住所がない場合でも大丈夫
住むところがない人でも申請できます。
まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
ホームレス状態、ネットカフェ生活、友人宅を転々としている場合でも、現在いる場所の福祉事務所で申請可能です。

ステップ2: 福祉事務所での相談
相談窓口での流れ
- 受付で「生活保護の相談」と伝える
- 予約不要、当日受付可能な福祉事務所がほとんど
- 相談員(面接員)との面談
- 現在の生活状況を詳しく聞かれます
- 収入、資産、家族構成、健康状態など
- 制度の説明を受ける
- 生活保護の仕組み
- 受給の条件
- 申請後の流れ
相談時に聞かれること
主な質問内容:
- 現在の収入はありますか?
- 貯金はどのくらいありますか?
- 持ち家や車などの資産はありますか?
- 親族から援助を受けられますか?
- 働ける状態ですか?健康状態は?
- なぜ生活保護が必要ですか?
正直に答えることが重要です。
虚偽の申告は不正受給となり、後で大きな問題になります。

ステップ3: 申請書類の提出
主な申請書類
保護の開始を申請する者は、氏名や住所又は居所、保護を受けようとする理由、資産及び収入の状況、その他保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項等を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければなりません。
必要書類一覧
- 生活保護申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 扶養義務者届
- 同意書(資産・収入調査への同意)
- その他、世帯の状況に応じた書類
書き方のサポート: 福祉事務所の職員が書き方を丁寧に教えてくれますので、わからないことは遠慮なく質問してください。
特別な事情がある場合
申請書を作成することができない特別な事情があるときは、申請書なしでも申請できます。
文字が書けない、病気で書類作成が困難な場合でも申請は可能です。口頭での申請も認められています。

申請後の調査と審査の流れ

調査の内容
保護の申請があると、地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問等をして、生活の状況や保護の要件を満たしているか調査します。

主な調査項目
1. 家庭訪問調査
- 実際の生活状況の確認
- 住居の状況(家賃、広さ、設備)
- 家財道具の確認
- 同居人の有無

2. 資産調査
- 預貯金の照会(金融機関への調査)
- 生命保険の契約状況
- 不動産の所有状況
- 自動車の所有

3. 収入調査
- 給与収入の確認
- 年金の受給状況
- その他の収入源

4. 扶養照会
- 三親等以内の親族への扶養の可能性確認
- ただし、DVや虐待がある場合、10年以上音信不通の場合などは省略可能
審査期間
申請した日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないか決定します。
標準的なスケジュール:
- 申請日: 0日目
- 家庭訪問: 3〜7日目
- 各種調査: 5〜10日目
- 審査会議: 10〜12日目
- 決定通知: 14日以内
決定通知
生活保護を受けられるかどうかの決定は書面でお知らせが来ます。
承認された場合
- 保護決定通知書が届く
- 生活保護費の支給開始
- 担当ケースワーカーの決定
不承認の場合
- 不承認理由が書面で通知される
- 不服がある場合は再審査請求が可能
生活保護の支給額と内容

8つの扶助
生活保護は、必要に応じて以下の扶助が支給されます:
1. 生活扶助 日常生活に必要な費用(食費、光熱費、被服費など)
2. 住宅扶助 家賃に相当する費用(上限あり)
3. 教育扶助 義務教育に必要な学用品費など
4. 医療扶助 医療費の全額補助
5. 介護扶助 介護サービスの自己負担分補助
6. 出産扶助 出産に掛かる費用
7. 生業扶助 就労に必要な技能習得費用や高校の費用など
8. 葬祭扶助 葬式に掛かる費用
支給額の計算方法
最低生活費と世帯の収入(年金や就労収入など)を比較し、最低生活費に不足する分を生活保護費として支給します。

計算式:生活保護費 = 最低生活費 – 収入
具体的な支給額例
単身世帯(東京都23区)の場合
65歳以上・単身
- 生活扶助: 約79,000円
- 住宅扶助: 53,700円(上限)
- 合計: 約132,700円
30代・単身・就労可能
- 生活扶助: 約83,000円
- 住宅扶助: 53,700円(上限)
- 合計: 約136,700円
複数世帯の場合
母子世帯(母+子2人、東京都23区):
- 生活扶助: 約160,000円
- 住宅扶助: 69,800円(上限)
- 教育扶助: 約5,000円
- 合計: 約234,800円
高齢者夫婦世帯(65歳以上×2人、東京都23区):
- 生活扶助: 約130,000円
- 住宅扶助: 64,000円(上限)
- 合計: 約194,000円
支給方法
支給方法
- 銀行口座への振込(原則)
- 福祉事務所窓口での現金受取(例外)
支給日
- 毎月1日〜5日頃(自治体により異なる)

よくある誤解と不安を解消
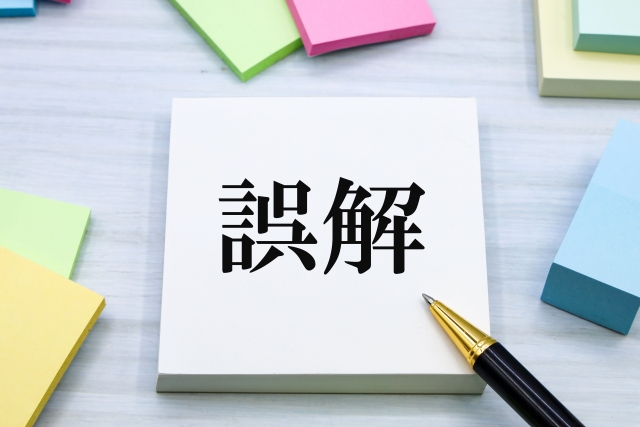
誤解1: 「持ち家があると受けられない」
A. 持ち家がある人でも申請できます。
居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
売却価値が低い、住宅ローンが完済している、売却すると住む場所がなくなるなどの場合は、持ち家を保有したまま受給できる可能性があります。
誤解2: 「働いていると受けられない」
A.働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます。

収入があっても、最低生活費を下回っていれば、その差額が支給されます。
誤解3: 「親族に必ず連絡される」
A.扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
親族と疎遠、DVや虐待の経歴がある、長期間音信不通などの場合は、扶養照会が省略されます。
誤解4: 「一度受けたらやめられない」
A.生活保護はいつでも辞退できます。

収入が増えて最低生活費を上回れば自動的に廃止になりますし、自分の意思で辞退することも可能です。
誤解5: 「車を持っていると絶対ダメ」
A.自動車については処分するのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
障害があって通院に必要、公共交通機関が利用できない地域での通勤に必要などの場合は、例外的に保有が認められます。
申請時の注意点とトラブル対処法

「水際作戦」への対処
一部の福祉事務所では、申請を受け付けない「水際作戦」と呼ばれる不適切な対応があると報告されています。

不適切な対応例:
- 「まだ申請できません」と追い返される
- 「親族に相談してから」と言われる
- 申請書を渡してもらえない
- 「施設に入ることに同意することが申請の条件」と言われる(これは誤り)
対処法
- 「申請します」とはっきり伝える
- 相談ではなく「申請」という言葉を使う
- 申請は口頭でも可能
- 書類がなくても申請の意思表示があれば受理義務がある
- 支援団体に相談する
- NPO法人
- 生活困窮者支援団体
- 弁護士や行政書士に相談
- 無料法律相談を活用
申請時の心構え
1. 正直に話す 収入や資産を隠すと後で不正受給となり、返還請求や刑事罰の対象になります。
2. わからないことは質問する 制度が複雑なのは当然です。遠慮せず質問してください。
3. 記録を残す
- 相談日時
- 担当者の名前
- 言われたこと これらをメモに残しておくと、トラブル時に役立ちます。
4. 同行支援を活用 一人で不安な場合、支援団体の同行支援サービスを利用できます。
よくある質問

Q1: 福祉事務所に行くのが怖いです…
A: その気持ちは多くの方が感じています。生活保護を必要とすることは、どなたにでもあり得ますので、ためらわずに相談してください。
福祉事務所の職員は生活に困っている方を支援するのが仕事です。怖がる必要はありません。どうしても一人が不安な場合は、信頼できる人や支援団体に同行を頼むこともできます。
Q2: 仕事を探していますが、すぐに働けそうにありません。申請できますか?
A: はい、申請できます。求職中であっても、現在の収入が最低生活費を下回っていれば受給できます。生活保護を受けながら就職活動を行い、就職が決まった後も一定期間は生活保護を受けながら働くことができます。
Q3: 外国籍ですが、生活保護は受けられますか?
A: 一定の条件を満たす外国籍の方も受給できる場合があります。永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等などの在留資格があれば、人道上の観点から生活保護に準じた保護を受けられる可能性があります。福祉事務所に相談してください。

Q4: 生活保護を受けると制限されることはありますか?
A: いくつかの制限があります:
- 資産の保有制限(車、貴金属など)
- 生活保護費からの借金返済は原則不可
- 海外旅行は原則不可(特別な理由がある場合は相談)
- ギャンブルや過度な飲酒など、健全な生活を送ることが求められる
ただし、普通の生活を送る分には問題ありません。

Q5: 申請が却下されたらどうすればいいですか?
A: 不服がある場合は、以下の方法があります:
- 審査請求
- 決定を知った日から3ヶ月以内
- 都道府県知事に対して行う
- 再審査請求
- 審査請求の結果に不服がある場合
- 厚生労働大臣に対して行う
- 裁判
- 行政訴訟を起こす
弁護士や支援団体に相談することをおすすめします。
Q6: 申請から支給までの生活費がありません
A: 生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」をご利用いただける場合もあります。
福祉事務所で相談すれば、つなぎ資金の案内や、緊急の支援について教えてもらえます。
まとめ:生活に困窮したら福祉事務所に相談しよう

福祉事務所での生活保護申請|重要ポイント
1. 生活保護は国民の権利 憲法で保障された権利であり、決して恥ずかしいことではありません。
2. 福祉事務所が申請窓口 お住まいの地域の福祉事務所で相談・申請ができます。
3. 必要書類が揃っていなくても申請可能 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。まずは相談に行くことが大切です。
4. 審査期間は原則14日以内 申請から2週間程度で結果が出ます。
5. 支給額は最低生活費-収入 地域や世帯構成により異なりますが、単身で月10万円〜13万円程度が目安です。
6. 持ち家・就労中でも申請可能 条件次第では、持ち家を保有したまま、働きながらでも受給できます。
7. 困ったときは支援団体に相談 一人で悩まず、NPO法人などの支援団体に相談しましょう。
最新データで見る生活保護の現状
- 2024年の申請件数は25万5,897件で5年連続増加
- 受給者数は約200万人
- 高齢者世帯が全体の55%以上
これらのデータが示すように、生活保護は決して特別なものではなく、多くの方が利用している制度です。
こんなときは躊躇せず福祉事務所へ
- 収入が少なく生活が苦しい
- 病気や怪我で働けなくなった
- 高齢で年金だけでは生活できない
- 失業して貯金が底をついた
- ホームレス状態、住む場所がない
- DVから逃げてきて頼れる人がいない
生活保護を必要とすることは、どなたにでもあり得ますので、ためらわずに相談してください。
相談窓口
お住まいの福祉事務所
- 市役所・区役所で「生活保護担当課」を尋ねる
- 厚生労働省ウェブサイトで福祉事務所一覧を確認
支援団体
- NPO法人
- 生活困窮者自立支援制度の相談窓口
- 社会福祉協議会
生活保護は、憲法で保障された国民の権利です。生活に困ったときは、一人で抱え込まず、福祉事務所に相談することから始めてください。
あなたの生活を守るために、この制度があります。勇気を出して一歩を踏み出しましょう。
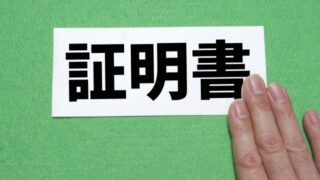














コメント