「生活保護受給者」と聞くと、あなたはどんなイメージを持つでしょうか。
- 働かない人
- 高齢者
- 不正受給者
- 怠け者
このようなイメージを持つ人は少なくありません。
しかし、元ケースワーカーとして断言します。
生活保護受給者は「特別な人」ではなく、誰でもなり得る存在です。
病気、事故、失業、離婚、DV、高齢、障害等、こうした人生の不測の事態により、生活が困窮するのは誰にでも起こりえます。
この記事では、
- 生活保護受給者とは何か
- 受給の条件
- 生活保護受給者の実態
- 生活保護の支給額
- 生活保護受給者に対する誤解
- 生活保護の問題点
- 今後の課題
について、徹底的に解説します。
生活保護制度を理解することで、偏見を減らし、必要な人が必要な支援を受けられる社会に近づけると信じています。

生活保護受給者とは?制度の基本と定義

生活保護受給者とは、生活保護法に基づき、「国の定める最低限度の生活を維持できないため、生活費や医療費などの支給を受けている人」のことです。
生活保護制度は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を具体化するものとして設けられています。
つまり、生活保護受給者は「制度を利用している普通の市民」であり、後ろめたさを感じる必要はありません。
生活保護を受けられる条件

生活保護には厳格な条件があります。
次の4つが特に重要です。
① 資産がないこと
預貯金・車・保険・土地などの資産を生活費に当てられる場合は、保護は認められません。




② 働く能力を使っても生活できないこと
働ける人は働く必要があります。
ただし、病気や障害、育児、年齢などの理由で働けない人も多く、その場合は保護対象です。
③ 他の制度や扶養が使えないこと
生活保護制度を受給する前に他法他施策優先の原則があります。
- 年金
- 傷病手当
- 失業保険
- 家族等、扶養義務者からの援助
など、他制度が優先です。
④ 最低生活費より収入が少ないこと
生活保護は、世帯の収入が最低生活費を下回る場合に支給されます。

生活保護受給者の内訳と特徴

「生活保護受給者=働いていない人」という誤解がありますが、実際は多様です。
厚労省の統計では、受給者の理由は次の通りです。
- 高齢で収入がない(高齢者世帯)
- 病気・障害で働けない
- 母子家庭・シングル家庭
- 失業・倒産
- DV被害者
- ホームレス状態からの保護
「怠けているから受給している」という人は実際にはほとんどいません。

生活保護受給者はどれくらいいる?

最新の統計では、 生活保護受給者は約200万人前後を推移しています。
日本の人口の約1.6%程度で、決して多いとはいえません。
日本の生活保護の特徴的なところは、
- 高齢者の割合が増えている
- 単身世帯が急増
- 働きながら受給する「ワーキングプア」が増えている
ということです。
生活保護受給者の生活はどんなもの?支給額の目安

具体的にどれくらい支給されるのかを知ると、生活保護受給者の生活のイメージが掴めます。
※地域や年齢等、支給金額は条件で異なりますが、一般的な例を示します。
◯単身者(40代)
→ 約12~13万円+家賃扶助(最大5万円前後)
◯高齢者夫婦
→ 約11〜12万円+家賃扶助(6〜7万円)
◯母子家庭(母+子1人)
→ 約15〜17万円+家賃扶助
※子が学生の場合は追加で教育扶助・生業扶助の支給もあり。
このように、生活保護の支給金額は贅沢できる金額ではないが、最低限の生活は何とか維持できる程度であることが分かります。

生活保護受給者がよく指摘される「誤解と偏見」
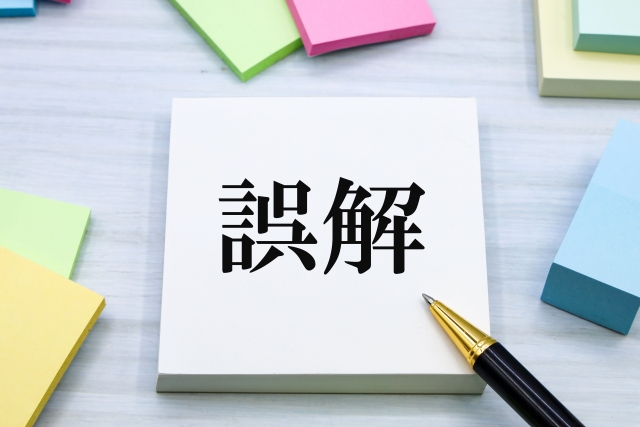
生活保護には誤解が非常に多いです。
ネットで特に多い誤解をまとめ、正しい情報を示します。
誤解①働かずにお金をもらっている
確かに高齢者の方や病気、障害をお持ちの方は働くことができないため、働かずにお金をもらっているのは、ある意味正しいです。
しかし、働きながら生活保護を受給している生活保護受給者も少数ですがいます。

また、病状調査の結果、働ける人には就労指導を行っています。


誤解②不正受給だらけ
生活保護の不正受給が発覚すると、マスメディア等で大体的に報道されるため、生活保護=不正受給だらけのイメージを持たれている方がいますが、実際の不正受給は全体の1〜2%程度と言われています。

誤解③パチンコしているから違反
「生活保護受給者がパチンコをしている!不正受給だ!」と福祉事務所によく問い合わせがありますが、生活保護受給者がパチンコをすることは法律的にも制度上も禁止されていません。
生活保護受給者がパチンコをしていても何ら問題はありません。

誤解④生活保護受給者は楽している
生活保護の支給金額は最低限であり、外食をしたり、お酒やタバコを吸うことなどはできますが、贅沢をすることは、ほぼ不可能です。


生活保護受給者に対する誤解があると、本当に生活保護を必要としている人が申請をためらい、命に関わる問題が発生するため、正しく生活保護制度について理解しましょう。
生活保護受給者の生活上の制限(デメリット)

生活保護にはメリットがありますが、同時にデメリットも多いです。

①資産が持てない
生活保護受給者は車・貯金・保険などを原則持つことができません。
ただし、例外はあります。
② 収入申告が必要
毎月福祉事務所に収入申告をする必要があります。
たとえ収入が一切なくても収入申告をする義務があります。
もちろん、給料や年金、扶養義務者からの援助等、何らかの収入があった場合は必ず申告しなければなりません。


申告しない場合は不正受給とみなされてしまい、最悪の場合、生活保護の停止・廃止になります。

③転居・旅行に制限
生活保護受給中は無断で引っ越すことはできません。

また、旅行等、長期間、家を留守にする場合は、必ずケースワーカーに相談をする必要があります。

無視して無断で転居・旅行をした場合は、居住実態なしとみなされ生活保護の廃止になる可能性があります。
④社会的偏見
生活保護受給者に対する社会的偏見は根強くあります。
基本的にケースワーカーが訪問調査をする場合等、生活保護受給者であることが近所の方にバレないように細心の注意を払いますが、どうしてもバレてしまうことはあります。

⑤生活保護費は必要最低限
生活保護費は決して多くはありません。
娯楽や趣味に使える余裕はほぼありません。
母子家庭の場合は、教育扶助、生業扶助、各種加算等、様々な項目で生活保護費が追加されるため、比較的裕福な生活を送ることができますが、いずれは単身世帯になり、支給金額もどんどん減らされてしまうため、結局は働いた方が自由に使えるお金は圧倒的に多いです。



生活保護受給者は働ける?働くとどうなる?

生活保護受給中でも働くことは可能です。
むしろ働ける人は働くことが求められます。
働くと保護費は減る? → Yes
就労収入がある場合、最低生活費との差額だけが支給されます。
ただし、基礎控除や各種控除があり、働いた分、全額が減額されるわけではありません。
そのため、生活保護受給中でも働いた方が、自由に使えるお金は増えます。

働くメリットは大きい
生活保護受給者は働くことで
- 貯金が少しできる
- 自立に近づく
- 生活に張りが出る
などのメリットがあり、生活の安定につながります。
生活保護受給者と「扶養照会」

申請時に親族へ「援助できるか」確認する扶養照会があります。

しかし、近年は以下のように緩和されています。
- DV・絶縁などは照会しない
- 援助する義務はない
- 拒否されても生活保護は受けられる
扶養照会はあくまで「お願い」であり、親族の義務ではないことを知っておいてください。
生活保護受給者に対する支援内容

生活保護を受けると、以下の扶助が利用できます。
- 生活扶助(生活費)
- 住宅扶助(家賃)
- 医療扶助(医療費0円)
- 介護扶助
- 生業扶助
- 教育扶助
- 葬祭扶助
特に医療扶助は受給者の生活を大きく支えています。
ケースワーカーが見た「生活保護受給者の本当の姿」
元ケースワーカーの経験から言えることは、生活保護受給者の多くは、困難の中で精一杯生きているということです。
- 病気で働けない
- 家族に頼れない
- シングルで育児に追われる
- 障害で仕事が難しい
- 高齢で収入がない
こうした背景が大半です。
「怠けている人」は少数派であり、むしろ「頑張りすぎて倒れた人」が多いと感じます。
生活保護受給者と不正受給問題
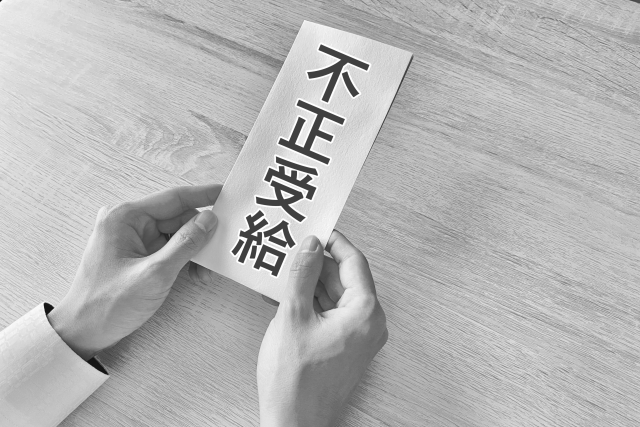
不正受給はメディアで大きく取り上げられますが、実際は全体の1〜2%ほどであり、非常に少ないです。
不正受給の例は、
- 収入を申告しない
- 同居人を隠す
- 資産を隠す
などで、悪質な場合は生活保護費の返還命令、徴収金、刑事罰もあります。
なお、誤解されやすいですが、パチンコは不正受給ではありません。
生活保護受給者が抱える課題

生活保護は重要な制度ですが、課題も多いです。
①社会的偏見
生活保護の申請をためらって餓死したり、犯罪に手を染めてしまうケースもあります。
②ケースワーカーの不足
ケースワーカー1人に対して100件以上を抱える自治体もあり、生活保護受給者に対する支援が十分にできていません。

③高齢化による生活保護受給者の増加
年金が十分にもらえる方は良いですが、無職の期間が長い方は年金の支給がない、もしくは年金支給額が少額のため、最低限度の文化的な生活を送ることはできません。
今後、ますます高齢者の生活保護受給者は増える見込みです。
④自立支援の難しさ
生活保護受給期間が長くなれば長くなるほど、無気力になっていくケースが多々あります。
上記のとおり、ケースワーカーもいっぱいいっぱいのため、就労支援が十分にできず、自立に向けた支援がなかなかうまくできていません。
生活保護受給者が安心して生活するために必要なこと

生活を安定させるために大切なのは次の3つです。
①ケースワーカーと良好な関係を築く
ケースワーカーは様々な指導をするため、鬱陶しく感じることもあると思いますが、ケースワーカーは生活保護受給者の味方です。
困ったことがあるときはケースワーカーに相談できるように良好な関係を築いておくことが大切です。
②無理のない範囲で就労を目指す
無理に働いた結果、病気等になってしまっては本末転倒です。
少しずつ自立に向けて、就労をしましょう。
少しの収入でも基礎控除等により、自由に使えるお金が増えるため生活の余裕につながります。
③制度を正しく理解して活用する
生活保護では、様々な扶助があります。
例えば教育扶助を申請することで、生活保護受給者の子どもでも部活動に必要な道具を購入するお金や部費が支給されます。
使える扶助を知らずに使わない生活保護受給者も多いため、どういう扶助をもらうことができるのか、情報収集は重要です。
まとめ:生活保護受給者は「制度を利用している市民」にすぎない

生活保護受給者は、怠け者でも特別な人でもありません。
人生の困難を乗り越えるために、制度を利用しているだけです。
- 高齢
- 病気
- 障害
- 失業
- 家庭のトラブル
等、生活保護を受給するようになった理由は様々ですが、誰にでも起こる可能性があります。
生活保護制度は、社会全体を支えるために必要な仕組みです。
必要なときは遠慮せず申請し、制度を正しく活用してください。




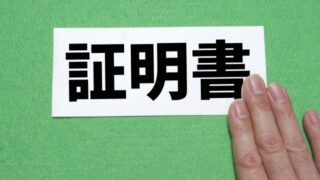








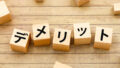
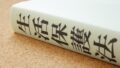
コメント