「家族がいると生活保護は受けられない?」
「親と同居しているけど、自分だけ受給できる?」
「夫婦で申請するにはどうすればいい?」
生活保護を検討している方の多くが、家族との関係で受給できるかどうかについて不安を抱えています。
実は、家族がいても条件を満たせば生活保護を受給することは十分に可能です。

本記事では、生活保護の基本的な条件から、家族構成別の受給方法、世帯分離の仕組み、扶養照会の対処法まで、家族と生活保護の関係について詳しく解説します。

生活保護とは?基本的な制度の仕組み

生活保護は、経済的に困窮している方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障する国の制度です。
日本国憲法第25条に基づき、すべての国民に保障された権利として位置づけられています。
生活保護の4つの基本原則
生活保護には、制度の運用を定める重要な原則があります
- 申請保護の原則:本人または家族からの申請に基づいて保護を開始する
- 世帯単位の原則:原則として世帯全体で保護の要否を判断する
- 無差別平等の原則:条件を満たせば誰でも平等に受給できる
- 最低生活保障の原則:健康で文化的な最低限度の生活を保障する
この中で特に重要なのが「世帯単位の原則」です。
これが家族構成と生活保護の関係に大きく影響します。
生活保護を受給するための4つの条件

生活保護を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。家族がいる場合も、この条件は変わりません。
条件1:世帯収入が最低生活費を下回っていること
最も基本的な条件が、世帯全体の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たないことです。

最低生活費は以下の要素によって決まります:
- 居住地域(1級地〜3級地の区分)
- 世帯人数
- 世帯員の年齢
- 障害の有無
目安となる最低生活費(東京都23区の場合)
- 単身世帯(20〜40歳):約13万円
- 夫婦2人世帯:約18万円
- 夫婦+子ども2人(4人世帯):約26万円
※住宅扶助や各種加算を含んだ概算額です。実際の金額は個別の状況によって変動します。
条件2:資産を活用すること
預貯金、不動産、自動車、有価証券、生命保険の解約返戻金など、活用できる資産がある場合は、まずそれらを生活費に充てる必要があります。
ただし、以下の資産は例外的に保有が認められる場合があります:
- 居住用の持ち家:資産価値が極端に高くない場合
- 自動車:通勤や通院に必要不可欠な場合、障害がある場合
- 預貯金:目的があり、貯金額も少額の場合



条件3:働く能力を活用すること
働ける能力がある場合は、その能力に応じて働く努力をすることが求められます。
ただし、以下のような場合は就労が困難と判断されます:
- 病気やケガで働けない(医師の診断書が必要)
- 精神疾患(うつ病、パニック障害など)で就労困難
- 高齢で就労が難しい
- 障害があり就労が困難
- 幼い子どもの育児で就労が制限される
働いている場合でも、収入が最低生活費を下回れば、その差額分の生活保護費を受給できます。


条件4:他の制度や親族の援助を優先すること
生活保護は「最後のセーフティネット」として位置づけられているため、以下を優先的に活用する必要があります:
- 年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)
- 各種手当(児童手当、児童扶養手当など)
- 雇用保険の失業給付
- 親族からの援助(扶養照会)
ただし、これらを活用しても最低生活費に満たない場合は、生活保護の対象となります。



家族構成別生活保護の受給条件と注意点

生活保護は「世帯単位」が原則ですが、家族構成によって受給の可否や方法が異なります。
以下、具体的なケース別に解説します。
ケース1:親と同居している場合
原則:親と同居している場合、世帯全体の収入が最低生活費を下回っているかどうかで判断されます。
例えば、自分が無職でも親に十分な収入がある場合、世帯全体では最低生活費を上回るため、生活保護は受給できません。

親の年金収入:月12万円
最低生活費:約15万円
結果:世帯収入(12万円)が最低生活費(15万円)を下回るため、差額の3万円が支給されます。
ただし、以下のような特別な事情がある場合、「世帯分離」が認められ、親と別世帯として扱われることがあります
- 親が働いているが、自分は障害や病気で全く働けない
- 親との関係が著しく悪い(DV、虐待の過去がある)
- 親の収入で自分の生活費を負担してもらっていない(家計が完全に別)

ケース2:夫婦で申請する場合
夫婦の場合は、原則として2人で1つの世帯として扱われます。
夫の収入:月8万円(パートタイム)
妻の収入:0円(病気で働けない)
合計収入:8万円
最低生活費(夫婦2人):約18万円
結果:差額の10万円が生活保護費として支給されます。
片方が働いていても、合計収入が最低生活費を下回れば受給できます。
ただし、働ける能力がある方は、就労の努力が求められます。

ケース3:子どもがいる家庭(ファミリー世帯)
子どもがいる世帯には、児童養育加算や母子加算(ひとり親の場合)などが最低生活費に加算されます。


世帯構成:父(40代)、母(30代)、中学生、小学生
最低生活費の内訳:
- 生活扶助:約17万円
- 住宅扶助:約6万円(地域による)
- 教育扶助:約5,000円×2人
- 児童養育加算:約1万円×2人
合計:約26万円
父の収入:月15万円
結果:26万円-15万円=11万円が生活保護費として支給されます。
また、児童手当や児童扶養手当を受給している場合、それらも収入として計上されますが、最低生活費に満たなければ差額が支給されます。
ケース4:ひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)
ひとり親世帯には母子加算(または父子加算)が認められ、通常よりも手厚い保護が受けられます。
世帯構成:母(30代)+子ども2人(小学生)
母の収入:パート月10万円
児童扶養手当:約4万円
最低生活費:約22万円(母子加算、児童養育加算を含む)
合計収入:14万円
結果:22万円-14万円=8万円が生活保護費として支給されます。
ケース5:高齢者と同居している場合
高齢の親と同居している場合も、世帯全体の収入で判断されます。
親が年金を受給していても、それが最低生活費を下回る場合は受給できます。
親の年金収入:月6万円
母の収入:パート月5万円
最低生活費:約15万円
結果:差額の4万円が生活保護費として支給されます。
世帯分離とは?家族がいても個別に受給する方法

世帯分離とは、同じ家に住んでいても、生活保護の審査において別々の世帯として扱う制度です。
これにより、家族の一部だけが生活保護を受給することが可能になります。
世帯分離が認められやすいケース
- 障害や病気で働けない人がいる場合:親は働いているが、子どもが重度の障害や難病で働けない
- 介護が必要な高齢者と働ける家族:親の介護で働けない人と、働ける兄弟が同居
- DV・虐待の過去がある場合:安全確保のため、家族との関係を分離する必要がある
- 経済的に完全に独立している場合:同居していても、収入も支出も完全に別々に管理している
世帯分離が認められにくいケース
- 単に「自分だけ受給したい」という希望のみの場合
- 家族が十分な収入を持ち、実際に生活費を援助している場合
- 働く能力があるのに就労の努力をしていない場合
世帯分離は住民票上の世帯分離とは異なります。
生活保護における世帯分離は、福祉事務所が実態を調査して判断します。

扶養照会とは?家族に知られずに受給できる?

生活保護を申請すると、原則として扶養照会が行われます。

これは、親や子ども、兄弟姉妹などの親族に「経済的援助ができるか」を確認する手続きです。
扶養照会の対象となる親族
民法第877条に基づき、以下の親族が扶養義務者となります:
- 直系血族:両親、子ども、祖父母、孫
- 兄弟姉妹
- 特別な事情がある場合:3親等内の親族(おじ、おば、甥、姪など)
扶養照会を避ける・断る方法
以下のような場合、扶養照会が省略される、または拒否できる可能性があります
- DV・虐待の過去がある場合:再度の被害を防ぐため、照会が行われない
- 長期間音信不通の場合:10年以上連絡を取っていないなど
- 親族が生活保護を受給している場合:援助する余裕がないため
- 親族が高齢や病気で援助できない場合
- 親族との関係が著しく悪い場合:客観的な証拠が必要
福祉事務所の担当者に、上記の事情を具体的に説明することで、扶養照会を避けられる可能性が高まります。
重要なポイント
扶養照会は「書面での確認」であり、親族が扶養を拒否した場合や返答がない場合でも、生活保護の受給は可能です。扶養照会があることで受給できなくなるわけではありません。

生活保護の申請から受給までの流れ

ステップ1:福祉事務所への相談(所要時間:1〜2時間)
お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当窓口に相談します。
この段階では正式な申請ではなく、制度の説明や他の支援制度の検討が行われます。
ステップ2:申請書の提出
生活保護を受けたい意思を伝え、申請書を提出します。
必要書類には以下のようなものがあります:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳のコピー(過去数ヶ月分)
- 給与明細や源泉徴収票(働いている場合)
- 年金証書、年金額通知書(年金受給者)
- 家賃の契約書、家賃の領収書
- 医師の診断書(病気やケガで働けない場合)
ステップ3:調査(約2〜4週間)
福祉事務所のケースワーカーが以下の調査を行います:
- 家庭訪問:実際の生活状況の確認
- 資産調査:銀行口座、不動産、自動車などの保有状況
- 扶養照会:親族への援助可能性の確認
- 就労能力調査:働ける能力の有無
ステップ4:決定通知(申請から原則14日以内、最長30日)
調査に基づき、生活保護の可否が決定され、通知書が送付されます。

ステップ5:受給開始
保護開始が決定されると、申請日に遡って生活保護費が支給されます。
その後は毎月決まった日に支給が続きます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 家族がいても生活保護を受けられますか?
A:はい、可能です。世帯全体の収入が最低生活費を下回っていれば、家族がいても受給できます。また、特別な事情がある場合は世帯分離が認められることもあります。
Q2. 親に知られずに生活保護を受けることはできますか?
A:原則として扶養照会が行われますが、DV・虐待の過去や長期間の音信不通などの事情があれば、照会が省略される可能性があります。福祉事務所に具体的に相談してください。
Q3. 働きながら生活保護を受けることはできますか?
A:できます。収入が最低生活費を下回る場合、差額分が支給されます。働くことは推奨されており、収入がある方が自立に向けた評価も高くなります。また、給料に応じて生活保護費の支給金額は減額されますが、基礎控除があるため、給料全額が減額されるわけではありません。結果的には働いた方が自由に使えるお金が増えます。
Q4. 生活保護を受けると家族に迷惑がかかりますか?
A:扶養照会が行われますが、親族が援助を拒否しても法的な問題はありません。また、親族に援助の義務が法的に強制されることもありません。
Q5. 家族の誰かが働いていると受給できませんか?
A:いいえ。世帯全体の収入が最低生活費を下回っていれば、誰かが働いていても受給できます。収入は全て申告し、不足分が支給されます。
まとめ:家族がいても諦めずに相談を

生活保護は、家族がいても条件を満たせば受給できる制度です。本記事のポイントをまとめます:
- 生活保護は世帯単位が原則だが、世帯分離という選択肢もある
- 世帯全体の収入が最低生活費を下回ることが基本条件
- 親と同居、夫婦、子育て世帯など、様々な家族構成で受給可能
- 扶養照会があっても、親族が拒否すれば受給できる
- DV・虐待の過去があれば、扶養照会を避けられる
- 働きながらでも、収入が少なければ差額が支給される
「家族がいるから無理」と諦める必要はありません。
生活に困窮している場合は、まずお住まいの地域の福祉事務所に相談してください。
生活保護は国民の権利です。条件を満たしている方は、ためらわずに申請しましょう。相談や申請をすることで、今の厳しい状況から抜け出す第一歩を踏み出すことができます。
困ったときの相談窓口:
・お住まいの市区町村の福祉事務所
・生活困窮者自立支援窓口
・社会福祉協議会
生活保護の申請は、電話での事前相談も可能です。まずは気軽に問い合わせてみましょう。







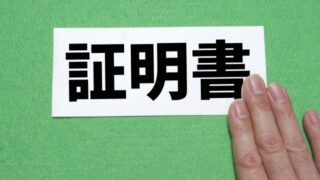







コメント