生活保護について調べると、必ず気になるのが「実際にいくらもらえるのか?」という金額の問題です。
しかし実際には、生活保護の金額は一律ではなく、世帯人数・地域・年齢・家賃・障害の有無など複数の条件で細かく変動します。
この記事では、複雑に見える生活保護費の仕組みを、誰でも分かるように丁寧に解説します。
2025年最新の基準に基づき、金額の「内訳」「計算方法」「実例」「増減のポイント」まで、生活保護を専門として扱う当サイトが総まとめします。

生活保護の金額はどう決まるのか?基本は「最低生活費 - 収入」

生活保護は、次の式で計算されます。
最低生活費 - 世帯の収入 = 支給される生活保護費
ここで重要なのは「最低生活費」という考え方です。

国が定める基準に基づき、生活に必要な金額を計算したもので、以下の費目に分かれています。
①生活扶助(食費・光熱水費などの日常生活費)
年代・家族構成・地域によって金額が変わります。

②住宅扶助(家賃)
地域の家賃相場に応じて「上限額」が決まっています。

③加算(教育扶助・障害加算・母子加算など)
特別な事情がある場合に追加されます。
この①〜③の合計が「最低生活費」となり、そこから収入(給与・年金など)を差し引いた金額が支給されます。
【生活扶助】実際にもらえる金額(2025年基準)

まずは生活費にあたる「生活扶助」ついてです。
地域は1級地~3級地に区分され、都会ほど高く、地方ほど低額になります。
■ 単身者(40代)生活扶助の目安
| 地域区分 | 金額(月額) |
|---|---|
| 1級地-1(東京・横浜など) | 約80,000~82,000円 |
| 1級地-2 | 約75,000円 |
| 2級地 | 約71,000円 |
| 3級地 | 約66,000円 |
※年齢や世帯人数で金額は変わります。
■ 2人世帯(母+子)生活扶助の目安
- 母(40代)…約75,000円(1級地-1)
- 子(10歳)…約53,000円
- 合計…約128,000円
子どもが小学生または中学生の場合は教育扶助、高校生の場合は生業扶助が別途追加で支給されるため、子どもの年齢によって金額が大きく変わります。

【住宅扶助】家賃として出る金額(地域ごとの上限)

家賃は、地域ごとに上限が決まっています。
実際に支給されるのは「実際の家賃」か「上限額」どちらか低い方です。
■ 地域別・単身者の家賃上限(目安)
| 地域 | 単身 | 2人 | 3~4人 |
|---|---|---|---|
| 東京都23区 | 約53,000円 | 約64,000円 | 約69,000円 |
| 政令市 | 約47,000円 | 約58,000円 | 約63,000円 |
| 地方都市 | 約38,000円 | 約45,000円 | 約52,000円 |
あくまで上限のため、実際には「この金額以内で住める家」に住む必要があります。
【加算】状況によって増える生活保護費

生活保護には、状況に応じて上乗せされる費用があります。
代表的な加算は以下の通りです。
教育扶助・生業扶助
子どもがいる世帯で小学生・中学生がいる場合は教育扶助、高校生がいる場合は生業扶助が支給されます。


ちなみに生活保護では大学生は想定していないため、大学生に対する追加支給はありません。

児童養育加算
18歳未満の児童を養育している場合に児童1人につき月額10,190円が上乗せされます。

母子加算
母子家庭の場合、
・第1子:約20,000円
・第2子以降:約10,000円
が上乗せされます。

障害者加算
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級に応じて、
約20,000~40,000円が上乗せされます。

介護・医療に関する加算
高齢者や病気のある方は支給金額が上乗せされます。

妊娠・出産に関する加算
妊娠していると支給金額上乗せされます。
支給金額は
- 妊娠6か月未満: 月額9,130円
- 妊娠6か月以上: 月額13,790円

また、産後についても最大6ヶ月間は産婦加算が支給されます。

【実例】生活保護はいくらもらえる?モデルケースで解説

では、実際の受給金額を具体的に計算してみます。
■ ケース1:単身者(40代・東京在住)
- 生活扶助:80,000円
- 住宅扶助:53,000円
- 合計:133,000円
支給額:133,000円-収入
給与が月50,000円あるなら
→ 133,000 − 50,000 = 83,000円支給
※厳密に計算する場合、給料収入については基礎控除があるため、上記の金額よりも多く支給されます。

■ ケース2:母子家庭(母40代+子10歳/大阪)
- 生活扶助:母74,000円+子52,000円=126,000円
- 母子加算:20,000円
- 住宅扶助:58,000円
- 合計:204,000円
収入が0円なら → 204,000円が満額支給
パートで月60,000円稼いでいる場合は
204,000 − 60,000 = 144,000円支給
となります。
■ ケース3:高齢単身者(70歳)
高齢者は生活扶助額が高く設定されています。
- 生活扶助:約66,000円(地方)~77,000円(都市)
- 住宅扶助:地域相場による(30,000〜50,000円程度)
東京の70代の場合は、12万〜13万円台が一般的です。
生活保護の金額は「最低限の生活」になるよう計算されている

よく誤解されていますが、生活保護は“生活に必要な最低限の金額”を支給する制度で、裕福に暮らすための制度ではありません。
生活保護の金額は、
- 物価
- 地域の賃料
- 年齢
- 家族構成
など細かいデータに基づき、科学的に算出されています。
過不足なく暮らせるよう調整されているため、実際に生活している人の多くは「贅沢はできないが、最低限の生活はできる」と感じています。

生活保護の金額が増えるポイント・減るポイント

■ 金額が増えるケース
- 障害がある(障害加算)
- 母子家庭(母子加算)
- 家賃が高い地域に住んでいる
- 医療費が多い(医療扶助は無料)
- 介護が必要
■ 金額が減るケース
- 収入が増えた(就労・年金・仕送り)
- 審査で家賃が高すぎると言われた
- 世帯の人数が減った
- 扶養義務者からの援助がある
特に収入がある場合は金額が減るため、働きながら生活保護を受ける「就労保護」の人は、毎月金額が変動します。
生活保護の金額は勝手に決められない ― 厳密な基準で決まる

生活保護はケースワーカーの「さじ加減」で金額が変わるものではありません。

国が決めた基準に基づき、必ず同じ計算方法で金額が決定されます。
そのため、同じ地域・同じ家族構成であれば誰でも同じ金額になるという公平性があります。
まとめ|生活保護の金額は「最低生活費」から収入を引いた金額

- 生活保護の金額は人によって異なる
- 生活扶助+住宅扶助+加算の合計が「最低生活費」
- 実際の支給額は「最低生活費-収入」
- 母子・障害・高齢者は金額が高くなる傾向
- 地域によって金額差が大きい(家賃が最大要因)
生活保護の金額は複雑に見えますが、実は明確なルールに基づいて決まっています。
もし「自分の場合はいくらになるか知りたい」という方は、ケースワーカーに相談すれば具体的な金額を計算してもらえます。
生活に困っているときは、ひとりで抱え込まず、まずは相談しましょう。










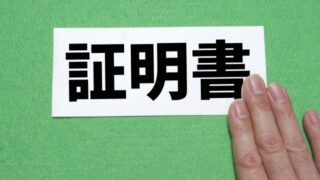



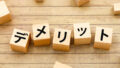
コメント