生活保護制度の中心となる支援が「生活保護費」です。
しかし実際には、
「生活保護費はいくらもらえるの?」
「生活保護費は何に使える?」
「どうやって決まるの?」
といった疑問を持つ人はとても多く、誤った情報がネット上に広まっているケースも少なくありません。
この記事では、元ケースワーカーの視点から、生活保護費の仕組み・支給内容・計算方法・使用範囲・増減の条件・注意点まで、わかりやすくまとめます。

生活保護費とは?

「生活保護費」とは、生活保護制度のもとで支給される各種扶助(費用)の総称です。
生活費だけでなく、住居費、医療費、介護費など生活に必要な費用すべてが対象となります。
生活保護費を構成する主な扶助は次の通りです。
①生活扶助(生活費)
食費・光熱費・衣服・日用品など、暮らしに必要な費用を支給します。

②住宅扶助(家賃)
上限額内で、家賃や共益費などを支給します。

③医療扶助(医療費)
生活保護受給者は病院での窓口負担が0円になります。
検査・薬・入院など、ほぼ全てが医療扶助の対象となります。

④介護扶助
要介護認定者の介護サービスを0円で利用可能。

⑤ 出産扶助
出産に掛かる費用を支給します。

⑥ 生業扶助
仕事に必要な技能習得費・資格取得費・通勤費などを支給します。
また、入学金や通学費等、高校通学に関する費用も生業扶助から支給されます。

⑦ 教育扶助
義務教育に必要な教材費・給食費・制服費などを支給します。

⑧ 葬祭扶助
身寄りがない場合などに葬祭費を支給します。
ただし、葬祭扶助で支給されるのは、必要最低限の葬祭費のため、イメージするような葬式ではなく、本当にこじんまりとしたものになります。

生活保護費とは、これらすべてをまとめた総称であり、単に「生活費」だけではありません。
生活保護費はいくらもらえる?

支給額は人によって全く違う
生活保護費は全国一律ではありません。
次の条件によって大きく変わります。
- 年齢
- 世帯人数
- 居住地(物価の違いによる級地区分)
- 家賃額
- 障害の有無
- 世帯の健康状態
- 就労収入など

生活保護費の算定式
生活保護費の基本的な計算は次のとおりです。
生活保護費 = 最低生活費(扶助の合計)- 世帯の収入
最低生活費より収入が少ない場合、その差額が支給されます。

逆に言うと、支給額だけを見るのではなく「最低生活費との差額」が生活保護費になるという点が非常に重要です。
生活保護費の使い道は自由?制限はある?

生活保護費のほとんどは「生活扶助」や「住宅扶助」など、生活の維持に必要な用途に使うことが前提ですが、基本的には使い道に厳しい制限はありません。
原則:使い道の自由は認められている
生活保護法は、受給者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を保障しています。


そのため、生活保護費の使い道を細かく制限することはできません。
- 食費
- 水道光熱費
- スマホ代
- 趣味(映画、雑誌、ゲームなど)
- 娯楽(パチンコ等ギャンブル)
- 衣類
- 交通費
これらはすべて「生活の維持に必要な出費」とみなされます。
ただし、浪費が過度な場合は指導の対象になる
例えば、
- ギャンブルに使いすぎて家賃を払えない
- 浪費により生活が破綻している
- タバコやお酒に依存している
- 家族や子どもの生活に支障が出ている
このような場合、ケースワーカーが指導を行います。

しかし生活保護費の浪費を理由に保護を打ち切ることはできません。
ただし、不正受給に当たる場合は別です。
生活保護費が増えるケース

生活保護費は状況によって増額されることがあります。
①家賃が上がった場合(住宅扶助の範囲内)
住み替えで家賃が上がる場合、上限内なら住宅扶助が増えます。
②世帯人数が増えた場合
子どもが生まれた、家族が合流したなどの場合は、増えた世帯人数に応じて生活扶助費等が増えます。
③障害や介護等で加算がつく場合
重度障害、母子家庭(父子家庭)、要介護等、各種加算の条件に該当した場合、生活保護費が増えます。
④物価上昇への対応(基準改定)
物価上昇に合わせて基準が改定されることがあります。
ただし、逆に生活保護費が減額改定されることもあります。
生活保護費が減るケース
逆に生活保護費が減るケースもあります。
①就労収入が増えた
収入認定されると、給料分、生活保護費が減ります。

ただし勤労控除などの各種控除があるため、働くほど実際に使えるお金は増える仕組みです。


②家賃が下がった
住宅扶助は実費支給のため、家賃が下がれば、その分、住宅扶助も減額されます。
③加算の終了
障害の改善、施設入所、子どもが成人した場合など、加算の条件を満たさなくなった場合は加算分、生活保護費が減額されます。
生活保護費が他人にバレることはある?

ケースワーカーは絶対に第三者へ漏らしてはいけない
生活保護制度には「守秘義務」があり、家主・学校・職場・親戚などに受給情報を伝えることは禁じられています。
唯一の例外は「扶養照会」ですが、扶養照会であっても生活保護費の具体的な内容までは伝えられません。

よくある誤解①:生活保護費は「税金の無駄」なのか?

生活保護費は税金で賄われていますが、誤解も多い分野です。
生活保護には“景気の自動安定装置”の役割がある
生活保護受給者が増えると「国が損する」と思われがちですが、実際には次のような効果もあります。
- 受給者が生活のために消費 → 経済が回る
- 生活困窮者の治療・支援 → 重症化を防ぎ医療費の増加を防ぐ
- 犯罪・孤立・ホームレス化の防止 → 社会リスクの軽減
つまり、生活保護費は社会の安定を支える“必要なコスト”です。
よくある誤解②:生活保護費は「働かずにもらえるお金」?

これもよくある誤解ですが、生活保護は「働けるのに働かない人の制度」ではありません。
ケースワーカーは受給者に対して、
- 求職活動
- 職業訓練
- 資格取得
- 健康管理
- 家庭支援
- 障害や病気の改善支援
などを継続的に指導します。
生活保護はあくまで「自立を促す制度」であり、長期的に働けるようにサポートする仕組みです。
生活保護費で購入できないものは?

基本的に生活保護費の使い道は自由ですが、次のようなものは原則不可または制限があります。
①高額資産(貴金属・高級家具・高級家電など)
貴金属や宝飾品などは資産とみなされます。
購入したとしても、売却指導の対象になります。
②自動車・バイクの購入
就労上必要なケースを除き、自動車・バイクは所有も購入もできません。
知人・友人から無料でもらった場合も売却指導の対象になります。


③投資目的の出費(株、仮想通貨、FXなど)
生活保護費で資産運用することは原則禁止です。
生活保護費は健康で文化的な生活を保障するための制度のため、税金を使って資産を増やす行為は禁止されています。
資産運用している場合は、売却指導の対象となり、資産運用で得た儲けは収入認定をされます。
なお、生活保護受給中でも預貯金は可能です。

生活保護費の管理が苦手な場合の対応

生活保護受給者の中には、
- 発達障害
- 知的障害
- 精神疾患
- 高齢による判断能力低下
などにより、お金の管理が難しい人もいます。
その場合、
- 生活保護費の代理納付(家賃などを代わりに支払う制度)
- 成年後見制度
- 生活困窮者自立支援制度
- 家計管理支援
などを利用しながら生活を安定させる方法があります。
まとめ:生活保護費は「自立のための支援」

生活保護費には多くの誤解がありますが、本来の目的は明確です。
「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援すること」
生活保護費は単なる現金給付ではなく、医療・介護・教育・住まい・就労など、生活全体を支える包括的な仕組みです。
制度を正しく理解することで、必要な人が安心して利用できる社会に近づきます。
生活保護を検討している方も、関わる支援者も、ぜひこの記事を参考にしてください。




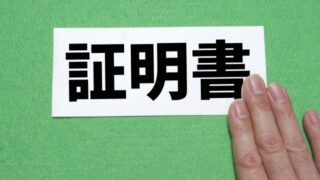










コメント