生活保護制度は、生活に困窮し、最低限度の生活ができない人を支えるための社会保障制度です。
「最後のセーフティネット」として非常に重要な制度ですが、一方で生活保護にはデメリットも多く、受給後に「こんなはずじゃなかった」と戸惑う人も少なくありません。
ネット上には誤った情報も多いため、この記事では元ケースワーカーの視点から、
- 生活保護を受けるデメリット
- 受給者が実際に困るポイント
- 誤解されがちな部分
- 生活保護と上手に付き合う方法
について、元ケースワーカーの立場から分かりやすく解説します。
生活保護を否定する意図はありません。
しかし、受給する以上は制度のルールや制限を正しく理解しておく必要があります。

- 生活保護を受ける主なデメリット一覧
- デメリット①資産の保有に制限がある
- デメリット② 収入申告と収入差引で「働いても手取りが増えにくい」
- デメリット③生活上の自由度が低くなる
- デメリット④ 転居や旅行に制限がある
- デメリット⑤ 偏見によるストレスが大きい
- デメリット⑥ 扶養照会が行われる(ただし近年は緩和方向)
- デメリット⑦ 医療扶助の利用で病院が制限されることもある
- デメリット⑧ クレジットカードやローンが組めないことがある
- デメリット⑨ 保護費が停止・減額されるリスク
- 【誤解】生活保護=デメリットだらけではない
- 生活保護のデメリットを小さくするためのポイント
- まとめ:生活保護にはデメリットはあるが、必要な人は利用すべき制度
生活保護を受ける主なデメリット一覧

まず結論として、生活保護のデメリットは以下の通りです。
- 資産保有に制限がある(車・貯金・保険など)
- 収入の申告義務が重い(収入のほぼ全額が保護費から差し引かれる)
- 金銭的に自由度が低くなる
- 転居や旅行に制限や許可が必要
- 世間から偏見を持たれやすい
- 「扶養照会」が行われることがある
- 就労指導を受ける場合がある
- 医療扶助の仕組みによって病院選びに制限が出ることがある
- スマホ・ネット契約、クレジットカードなどが制限される場合がある
- 保護費が停止・減額されるリスクが常にある
ここからはひとつずつ詳しく説明します。
デメリット①資産の保有に制限がある

生活保護受給中は、原則として資産を持つことができません。
・車
・貯金
・生命保険
・高額なスマホ・パソコン
・高価な時計や宝石
などは「処分して生活費に充てられる」と判断されれば、売却が求められます。
ただし、仕事で必要な車や、地元の交通事情などによっては例外的に認められる場合もあります。
デメリット② 収入申告と収入差引で「働いても手取りが増えにくい」

生活保護には収入申告義務があります。
バイト代、年金、家族からの仕送り、ポイント還元まで申告対象になることがあります。
さらに、働いて得た収入は、保護費から差し引かれる(控除後の収入を除く)ため、手元に残るお金はわずかです。
その結果、「働いても得にならない」「モチベーションが上がらない」と感じる人が多いのも現実です。
ただし、就労収入には基礎控除などがあり、完全にゼロになるわけではありません。
とはいえ、収入が多く残る仕組みとは言い難いです。

デメリット③生活上の自由度が低くなる

生活保護を受けている間は、日常生活で自由に使えるお金が限られるため、
・好きな服を買う
・外食する
・趣味に使う
・家電をそろえる
といった行動が難しくなります。
特に単身世帯では、手元に残る生活費はかなり少ないため、節約が必須です。
結果として「生活の満足度が下がった」と感じる人も多いです。
デメリット④ 転居や旅行に制限がある

生活保護受給中は引っ越しや長期外出に許可が必要です。
- 勝手に引っ越す
- 長期間家を空ける
- 県外に旅行する
こうした行動は認められないことが多く、無断で行うと生活保護の停止・廃止に繋がります。

特に「旅行」については、医療扶助を受けている場合に問題が生じやすく、トラブルを避けるために制限されることもあります。

デメリット⑤ 偏見によるストレスが大きい

生活保護に対する社会の理解はまだ十分とはいえません。
そのため受給者は、
- 差別的な目
- 差別的な目
- 偏見
- 誹謗中傷
といった精神的なストレスを受けることがあります。
SNSでも誤った情報が拡散されがちで、受給していることを周囲に言いづらいと感じる人も多いです。
デメリット⑥ 扶養照会が行われる(ただし近年は緩和方向)

生活保護申請時には、原則として親族への扶養照会(援助できるかの確認)が行われます。


これに対して「親に知られたくない」「家族関係が最悪で連絡されたくない」と不安を感じる人は多いです。
ただし近年は本人の事情が重視され、DVや絶縁状態などの場合は照会が省略されることも増えています。
デメリット⑦ 医療扶助の利用で病院が制限されることもある

生活保護の大きなメリットは医療費が0円になることですが、医療扶助の仕組み上、以下のような制限が出ることがあります。
- 指定医療機関しか使えない場合がある
- 高額な治療や自由診療は対象外
- 歯科治療などで使える素材が限られる
「無料だから自由に医療を受けられる」というわけではありません。
デメリット⑧ クレジットカードやローンが組めないことがある

生活保護受給中は、社会的信用が下がるため、
- クレジットカード審査に通りづらい
- ローン契約ができない
- スマホ本体の分割契約も不可になる場合がある
など、契約面で不利になることがあります。
特にスマホは生活必需品となっているため、この制限に困る受給者は多いです。

デメリット⑨ 保護費が停止・減額されるリスク
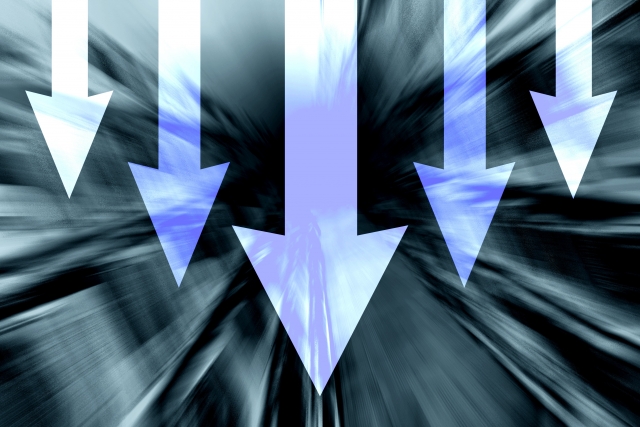
生活保護は「権利」であると同時に「義務」もあります。
- 収入申告の忘れ
- ルール違反
- 扶助の不正利用
- 就労指導への非協力
などがあると、生活保護費の不正受給とみなされ、徴収・返還による生活保護費の天引き(減額)や生活保護自体を廃止・停止されることがあります。

少しのミスが大きな問題につながることもあり、精神的に負担を感じる人は少なくありません。
【誤解】生活保護=デメリットだらけではない

ここまでデメリットを多く挙げてきましたが、生活保護にはもちろん大きなメリットもあります。
- 最低限の生活が保障される
- 医療費がかからない
- 家賃も一部または全額支給される
- 返済不要
- 就労支援が受けられる
メリット・デメリット両方を理解したうえで、必要な人は遠慮せず活用すべき制度です。
生活保護のデメリットを小さくするためのポイント

デメリットがあるからといって、不安になる必要はありません。
工夫次第で負担を減らすことができます。
①ケースワーカーと良好な関係を築く
生活保護制度は複雑なので、困ったらすぐにケースワーカーに相談することが大切です。
ケースワーカーからの指示をよく聞くなど、ケースワーカーとは良好な関係を築けるように努力しましょう。

②収入申告を確実に行う
収入申告の漏れ・遅れはトラブルの原因になります。
収入が全くない場合は大丈夫ですが、収入があった場合は必ずケースワーカーに伝えましょう。
③無理のない範囲で就労を目指す
病状調査の結果、就労可能であれば、就職活動を行いましょう。

ハローワークに行く他、生活保護では、就労支援もあるので、そちらも積極的に活用しましょう。

収入が増えれば、少額ではありますが、基礎控除等もあるため、生活の自由度が上がります。
④医療機関・制度を正しく使う
医療扶助の枠内でも十分な支援を受けられます。

しかし、病院から受診拒否をされてしまうと、どこの病院にも通院できなくなってしまいます。
そのため、医療費がタダだからと言って、無闇矢鱈に病院い行くのは避けましょう。
また、医師や看護師の言うことはキチンと聞きましょう。
まとめ:生活保護にはデメリットはあるが、必要な人は利用すべき制度

生活保護には、資産制限や収入申告などのデメリットが確かに存在します。
しかし、それでも生活が成り立たない人にとっては、欠かすことのできない制度です。
大切なのは、「制度を正しく理解したうえで利用すること」です。
制度を知っておけば、安心して生活を立て直し、自立に向けて動いていけます。
生活保護は「甘え」ではなく、再出発のための制度です。必要なときは遠慮せず利用してください。








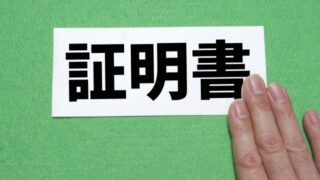






コメント