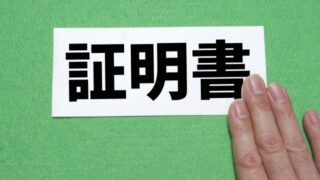生活保護を申請する際、もっとも質問が多いのが「持ち家があるけれど生活保護は受けられるのか?」という点です。
結論から言うと、
●ローンが残っている家・土地 → 生活保護は受給できない
●ローンが完済済みの家・土地 → 条件次第で受給可能
という明確なルールがあります。
この記事では、元ケースワーカーの視点から 生活保護と持ち家の関係、ローンの扱い、売却指導、リバースモーゲージなど、申請者が最も誤解しやすい部分を分かりやすく解説します。
生活保護申請を検討している方や、家をどうすればいいか悩んでいる方は必ず参考になります。
生活保護と持ち家の基本ルール

まず最初に押さえるべきポイントは以下の通りです。
生活保護は「国がお金を出して個人の資産形成を助ける制度ではない」という原則があります。
そのため、ローン返済中の家を維持しながら生活保護費を受け取ることは認められません。
もし認めてしまうと、
生活保護費で住宅ローンを払う= 国の税金で個人の資産を増やす
ことになります。
このような不公平が生じるため、ローンが残っている場合は、法律上もケースワーカーの判断基準としても「不可」です。
【結論】ローンが残っている家は生活保護では維持できない

ローンの残った家・土地 → 生活保護の受給はできない
理由はシンプルで、生活保護費をローンの返済に使うことはできないためです。
また、住宅ローン返済は「生活扶助」や「住宅扶助」の対象外です。


つまり、生活保護申請を行うのであれば、以下のいずれかになります。
- 住宅ローンを完済する
- 家を売却する
- 任意売却・競売に進む
ローンを残したまま「住み続けたいので生活保護を…」という相談は非常に多いですが、制度上、不可能です。
【例外】ローンが完済済みなら家・土地があっても生活保護は受けられる

ローン完済済み → 家を持ったまま生活保護を受けられる
ただし、家が「活用できる資産」に該当するため、ケースワーカーからは活動指導が行われます。
誤解している人が非常に多くいますが、活動指導=売却指導ではありません。
活用とは以下のような意味です。
- 持ち家に住み続ける(家賃を支払う必要がないため)
- 貸して家賃収入を得る
- 売却を検討する(高額な場合)
つまり、「必ず売却しろ」という意味ではありません。
生活保護制度の目的は「最低限度の生活保障」であり、家に住むことで最低生活費が下がるのであれば、そのまま住み続けることが認められるのです。

持ち家の資産価値が高い場合はどうなる?

資産価値が高い家は、生活に必要以上の資産と判断され、次のような対応が行われます。
- 売却できる場合 → 売却指導
- 居住継続した方が良いと判断した場合 → リバースモーゲージ検討
特に持ち家の価値が高いと、生活保護の前に「処分可能な資産」と判断されます。
リバースモーゲージの利用条件

持ち家を担保に生活費を借りる制度=リバースモーゲージ
銀行が提供するものもありますが、条件が厳しいため生活保護との関係では社会福祉協議会(社協)のリバースモーゲージが主に検討されます。
社協リバースモーゲージの条件(全て満たす必要あり)
- 生活保護の受給要件を満たしている
- 居住用家屋の資産価値が500万円以上
- 抵当権・担保権などが設定されていない
- 申込者または夫婦が65歳以上
- 単独名義(夫婦なら共有可)
この制度を利用すると、リバースモーゲージの貸付で最低生活費を確保できるため生活保護は廃止なります。

ただし、貸付金が資産価値の70%(マンションは50%)に達するとリバースモーゲージの支給が停止されるため、停止後に生活困窮すれば再び生活保護を申請可能となります。

資産価値が低い場合は「持ち家に住み続ける」指導になる
リバースモーゲージが利用できず、売却しても生活が成り立たない場合は…
持ち家に住み続けることが最も生活費を抑えられるため、基本的には居住継続が認められます。
理由は簡単で、生活保護が家賃(住宅扶助)を支給する必要がなくなるためです。
所有物件を第三者に貸している場合の扱い

誰かに家・土地を貸しているケースでは、家賃が無料または近隣相場より明らかに低い場合は家賃の引き上げ指導を行います。
そして、その家賃収入は収入認定を行い、家賃収入では足りない分の生活費について生活保護で支給することになります。

生活保護は「利用可能な資産や収入を最大限活用する」ことが原則のため、相場より極端に安い家賃で貸している場合は改善を求められます。
空き家・誰も住んでいない家の扱い

誰も住んでいない家を所有している場合は、基本的に売却指導になります。
仮に客観的に見て明らかに売れなさそうな家・土地であっても、必ず売却するように不動産会社等への登録を済ませなければいけません。
さらに、申請者が賃貸住宅に住んでいる場合は、持ち家に転居できるのに賃貸住宅の家賃を生活保護が負担するのは不適切と判断されるため、持ち家への引越しを指導されることもあります。
なお、その場合の引越し費用については、生活保護から支給されます。

家を売却した場合の「返還」のルール

申請前から所有していた家を売却した場合、その売却代金は資産として扱われます。
そして、生活保護開始後に支給された生活保護費は返還対象となります。
理由は以下。
●本来、家を売却すれば生活できた可能性がある
↓
●よって、売却資産で保護費を返還するのが公平
この仕組みは制度上明確に定められており、不思議に感じるかもしれませんが、必ず生活保護費を返還しなければいけません。
もしも売却したのに、ケースワーカーへ報告しない場合は不正受給とみなされ、徴収金として罰則金まで取られる可能性もあるため、売却した場合は、必ずケースワーカーに報告しましょう。

なお、「報告しなければバレないのでは?」と思うかもしれませんが、ケースワーカーには調査権があるため、遅かれ早かれ必ずバレます。

■まとめ|家や土地があっても生活保護は可能。ただし条件は厳密

最後に、この記事のポイントを整理します。
- 住宅ローンが残っている → 生活保護は受けられない
- 住宅ローン返済済み → 条件次第で持ち家のまま生活保護が可能
- 活用指導=売却ではない
- 資産価値が高い場合は売却またはリバースモーゲージ
- 家・土地を貸している場合の家賃収入は収入認定される
- 空き家は売却指導の対象
- 売却後は保護費返還が必要になる
生活保護は「資産をどう活用するか」という観点が非常に重要です。
持ち家があっても決して申請を諦める必要はありませんが、制度に沿って正しく判断する必要があります。