「年金だけでは生活が苦しい…」「高齢になって貯金が底をついてしまった…」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、生活保護を受給している方の半数以上が65歳以上の高齢者世帯です。
令和3年のデータでは、約90万世帯の高齢者が生活保護を利用しており、決して特別なことではありません。
この記事では、高齢者の方が生活保護を受けるための条件や申請方法、受給額の目安、よくある疑問まで、分かりやすく徹底解説します。

高齢者と生活保護の現状

増え続ける高齢者の受給者数
生活保護は、憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するための制度です。
現在、生活保護受給者全体では約204万人ですが、そのうち高齢者世帯は約90万世帯以上で、全体の55%以上を占めています。
20年前と比較すると、高齢者の受給世帯数は増加傾向が続いています。
なぜ高齢者の受給者が増えているのか
高齢者の受給者増加の背景には、以下のような社会的要因があります:
- 年金受給額の減少: 物価上昇に対して年金額が追いついていない
- 消費税の増税: 1989年の3%から2019年の10%へと段階的に増税
- 単身高齢者の増加: 家族との同居率の低下
- 医療費の負担: 後期高齢者でも一部負担が必要な場合がある
- 老後資金の不足: 十分な貯蓄ができなかったケース
このような状況の中、生活保護は高齢者にとって重要なセーフティネットとなっています。
高齢者が生活保護を受けるための5つの条件

高齢者が生活保護を受けるための条件は、基本的には他の世代と同じです。
しかし、高齢者特有の事情も考慮されます。
条件1: 世帯収入が最低生活費を下回っていること【最重要】
これが最も重要な条件です。
世帯全体の収入(年金、給与、仕送りなど全て含む)が、厚生労働省が定める最低生活費を下回っている必要があります。

収入に含まれるもの
- 年金(国民年金、厚生年金など)
- 給与収入
- 仕送り
- 保険金
- 預貯金の利子
- 不動産収入
- その他あらゆる収入
この条件さえ満たしていれば、生活保護を受給できる可能性は非常に高くなります。
条件2: 資産を活用すること
生活保護は最後のセーフティネットです。
そのため、生活に利用できる資産がある場合は、まずそれを活用することが求められます。
売却が必要な資産
- 預貯金(ある程度の額がある場合)
- 土地・建物(持ち家)
- 生命保険(解約返戻金がある場合)
- 自動車(原則として)
- 貴金属・有価証券など
ただし例外もあります。
持ち家については、以下の場合は保有が認められることがあります
- 売却価値がほとんどない
- 売却すると生活に著しい支障がある
- 売却しても生活費に充てるほどの金額にならない

自動車やバイクについても、以下のケースでは保有が認められる場合があります。
- 通院に必要不可欠(公共交通機関が利用困難)
- 障害があり移動手段として必要


条件3: 働く能力を活用すること
年齢や健康状態に応じて、働ける場合は就労することが求められます。
ただし、高齢者の場合は以下の点が配慮されます。
- 75歳以上の後期高齢者は就労義務が事実上免除される
- 健康状態や体力に応じた判断がされる
- 無理な就労を強制されることはない
年金を受給している高齢者でも、働ける状態であれば軽度の就労を求められることがありますが、体調や年齢を考慮した現実的な範囲内での話となります。

条件4: 他の制度を優先して活用すること
生活保護以外に利用できる制度がある場合は、まずそちらを優先します。
高齢者が利用できる主な制度:
- 年金制度: 国民年金、厚生年金、遺族年金など
- 生活福祉資金貸付制度: 低所得世帯向けの貸付
- 医療費助成制度: 後期高齢者医療制度など
- 介護保険制度: 要介護認定を受けている場合
これらの制度を活用しても最低生活費に満たない場合、その不足分を生活保護で補うことができます。
条件5: 親族からの扶養を活用すること
三親等以内の親族に扶養能力がある場合、援助を求めることが原則です。

高齢者の場合の扶養義務者
- 子ども
- 孫
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
ただし、以下の点を理解しておくことが重要です。
扶養照会とは、生活保護を申請すると、福祉事務所から親族に「扶養照会」という確認の書類が送られます。
これは親族に扶養の可能性を確認するもので、扶養を強制するものではありません。

親族が扶養できない場合
- 親族から「扶養できない」との返答があった
- 親族から返答がなかった
- 親族との関係が疎遠・絶縁状態
- DVや虐待の経歴がある
このような場合は、扶養照会なしで生活保護を受給できます。
高齢者の生活保護受給額はいくら?

生活保護で受け取れる金額は、「最低生活費 – 世帯収入 = 生活保護費」という計算式で決まります。

生活保護費の構成
生活保護費は、以下の「扶助」の組み合わせで構成されます。
- 生活扶助 日常生活に必要な費用(食費、光熱費、被服費など)
- 住宅扶助 家賃に相当する費用(上限あり)
- 医療扶助 医療費の自己負担分を全額補助
- 介護扶助 介護サービスの自己負担分を全額補助
- 教育扶助 義務教育に掛かる費用
- 生業扶助 就労活動、資格取得、高校通学に掛かる費用
- 出産扶助 出産に掛かる費用を全額補助
- 葬祭扶助 葬儀に掛かる費用を全額補助
地域別・世帯別の受給額目安
生活保護費は、居住地域の「級地」によって金額が異なります。
都市部ほど高く、地方ほど低く設定されています。
東京23区の場合(1級地-1)
単身世帯(65歳以上)
- 生活扶助: 約71,000円〜79,000円
- 住宅扶助: 53,700円(上限)
- 合計: 約124,700円〜132,700円
夫婦世帯(65歳以上×2人)
- 生活扶助: 約117,000円〜130,000円
- 住宅扶助: 64,000円(上限)
- 合計: 約181,000円〜194,000円
大阪市の場合(1級地-1)
単身世帯(65歳以上)
- 生活扶助: 約70,000円〜78,000円
- 住宅扶助: 40,000円(上限)
- 合計: 約110,000円〜118,000円
地方都市の場合(2級地または3級地)
単身世帯(65歳以上)
- 生活扶助: 約60,000円〜68,000円
- 住宅扶助: 30,000円〜35,000円(上限)
- 合計: 約90,000円〜103,000円
年金受給者の場合の計算例
ケース1: 東京23区在住・単身・年金月額65,000円
- 最低生活費: 132,700円
- 年金収入: 65,000円
- 生活保護費: 67,700円
- 実際の収入: 132,700円(年金+生活保護)
ケース2: 地方都市在住・単身・年金月額50,000円
- 最低生活費: 95,000円
- 年金収入: 50,000円
- 生活保護費: 45,000円
- 実際の収入: 95,000円(年金+生活保護)
加算制度について
特定の条件に該当する場合、基本の生活保護費に加算されます。
冬季加算 寒冷地で冬期(10月〜4月頃)に暖房費として加算
- 札幌市など: 約12,000円〜13,000円/月
- 東京23区: 約2,000円〜3,000円/月

障害者加算 障害者手帳を持っている場合に加算
- 1級・2級: 約26,000円〜27,000円/月
- 3級以下: 約17,000円〜18,000円/月

生活保護の申請方法【ステップ別解説】

生活保護の申請は、以下の手順で進めます。

ステップ1: 福祉事務所への相談(事前相談)
まずは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談に行きます。
持参すると良いもの:
- 身分証明書
- 年金手帳・年金証書
- 通帳(直近数ヶ月分)
- 賃貸契約書
- 医療費の領収書(ある場合)
- 公共料金の請求書
- 印鑑
この段階で、生活保護の制度説明を受け、申請が可能かどうかの見込みを確認できます。
事前に確認すべきこと
- 持っている資産は生活のために活用したか
- 働ける人は能力に応じて働いているか
- 年金や手当は全て申請・受給しているか
ステップ2: 申請書類の提出
相談の結果、申請することになったら、必要書類を提出します。
主な申請書類:
- 生活保護申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 扶養義務者に関する届出書
- 同意書(資産・収入調査への同意)
福祉事務所で書類の書き方を教えてもらえますので、安心してください。
ステップ3: 調査(家庭訪問)
申請後、福祉事務所のケースワーカーが自宅を訪問し、生活状況を確認します。

調査される内容:
- 実際の生活状況
- 資産の有無
- 親族との関係
- 健康状態
- 年金の受給状況
正直に答えることが大切です。
虚偽の申告は不正受給となり、刑事罰の対象になる可能性があります。

ステップ4: 審査
提出された書類と調査結果を基に、福祉事務所で審査が行われます。
審査期間: 原則14日以内(最長30日)
ステップ5: 決定通知
審査結果が郵送で通知されます。
受給が決定した場合
- 福祉事務所で受給方法を決定(口座振込または窓口受取)
- 月の途中から申請した場合は日割りで支給
- 翌月から通常通りの支給
不承認になった場合
- 理由が記載された通知が届く
- 不服がある場合は再審査請求が可能
ステップ6: 定期的な報告
生活保護を受給した後も、定期的にケースワーカーの訪問があり、生活状況を報告する必要があります。
報告が必要な事項
- 収入の変動
- 資産の変動
- 家族構成の変化
- 住所の変更
- 健康状態の変化
年金を受給していても生活保護は受けられる?

結論: 受けられます!
これは非常に多い誤解ですが、年金を受給していても生活保護を申請・受給することは可能です。
年金と生活保護の併給の仕組み
生活保護は「最低生活費に満たない分を補う」制度です。
計算式:最低生活費 – 年金収入 = 生活保護費
つまり、年金を受給していても、その金額が最低生活費を下回っていれば、不足分を生活保護で受け取れます。

具体例
例: 東京都在住・75歳単身世帯
- 国民年金: 月額60,000円
- 最低生活費: 130,000円
- 生活保護費: 70,000円
- 実際の手取り: 130,000円
この場合、年金60,000円に加えて生活保護費70,000円を受け取り、合計130,000円で生活することになります。
年金受給者が知っておくべきポイント
1. 年金は必ず申請・受給する
年金を受給する権利があるのに申請していない場合、まず年金の申請が求められます。
生活保護は「他の制度を優先」するためです。
2. 遺族年金も収入として計算される
配偶者が亡くなって遺族年金を受給している場合も、その金額を含めて計算されます。
3. 年金が増額されたら報告が必要
年金額が改定されて増額した場合、福祉事務所への報告が必要です。
その場合、生活保護費は減額調整されます。
よくある質問と回答

Q1: 持ち家があっても生活保護は受けられますか?
A: 場合によっては受けられます。
以下の条件を満たす場合、持ち家を保有したまま生活保護を受給できることがあります。
- 売却価値が低い
- ローンが完済している
- 売却すると住む場所がなくなり、かえって生活に支障がある
- 住宅の資産価値が地域の基準を超えていない
ただし、ローンが残っている場合や、高額な資産価値がある場合は、売却を求められる可能性が高いです。
Q2: 生活保護を受けると家族に連絡が行きますか?
A: 原則として扶養照会が行われますが、連絡しない方法もあります。
扶養照会は原則として三親等以内の親族に送られますが、以下の場合は照会が行われません:
- 親族との関係が疎遠(10年以上音信不通など)
- DVや虐待の履歴がある
- 親族が生活保護を受給している
- 親族が70歳以上の高齢者
- 親族が重度の障害や疾病を抱えている
福祉事務所に事情を説明することで、扶養照会を避けられる可能性があります。
Q3: 生活保護を受けると老人ホームに入れませんか?
A: 入居可能な施設があります。
生活保護を受給していても、以下の施設には入居できます:
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 生活保護対応の有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
ただし、入居費用は住宅扶助の範囲内である必要があり、施設によっては生活保護受給者を受け入れていない場合もあります。
事前に福祉事務所やケアマネージャーに相談することをおすすめします。
Q4: 生活保護を受けると医療費は無料になりますか?
A: はい、原則として無料になります。
生活保護受給者は「医療扶助」により、以下の医療費が全額免除されます。
- 診察料
- 薬代
- 入院費
- 歯科治療費
- 訪問看護費

ただし、以下の点に注意が必要です。
- 指定医療機関での受診が必要
- 原則としてジェネリック医薬品を使用
- 美容整形など医療として認められないものは対象外

Q5: 生活保護を受けると介護サービスは利用できますか?
A: はい、自己負担なしで利用できます。
生活保護受給者は「介護扶助」により、介護保険サービスの自己負担分が全額免除されます。
- 訪問介護
- デイサービス
- ショートステイ
- 福祉用具のレンタル
- 住宅改修

要介護認定を受けている場合は、ケアマネージャーと連携して必要なサービスを利用できます。
Q6: 生活保護を受けると車は持てませんか?
A: 原則として持てませんが、例外があります。
以下の場合は、車の保有が認められることがあります。
- 通院に必要不可欠で、公共交通機関が利用困難な地域
- 障害があり、移動手段として車が必要
- 仕事に必要(自営業など)
ただし、これらは地域や個別の事情によって判断が異なるため、福祉事務所に相談することが必要です。
Q7: 生活保護を受けると貯金はできませんか?
A: 原則として貯金は認められません。
生活保護は「最低限度の生活」を保障する制度のため、基本的に貯金をする余裕はない想定です。ただし、以下の例外があります。
- 家具・家電等、購入目的のある貯金
- 少額の貯金
大きな貯金ができた場合、生活保護費を減額または停止される可能性があります。

Q8: 生活保護を受給すると社会的に不利になりますか?
A: 基本的に不利になることはありません。
生活保護の受給は法律で認められた権利であり、恥ずかしいことではありません。
以下の点を理解しておくことが重要です。
- 生活保護受給者であることは、本人の同意なしに他人に知られることはない
- 賃貸住宅の入居審査では、生活保護受給者専用の物件もある
- 年金受給と同じく、国の制度を利用しているだけ
全体の55%が高齢者世帯という事実からも、決して特別なことではありません。
まとめ:年金では生活が苦しい場合は相談を

高齢者が生活保護を受けるための条件や申請方法について解説してきました。
重要なポイントのおさらい
- 受給世帯の半数以上が高齢者: 決して珍しいことではありません
- 最も重要な条件は「収入が最低生活費を下回ること」: この条件を満たせば受給の可能性は高い
- 年金を受給していても申請可能: 不足分を生活保護で補えます
- 医療費・介護費が無料: 高齢者にとって大きなメリット
- 持ち家や車も条件次第で保有可能: 一律に処分が必要なわけではありません
生活保護を検討すべきケース
以下のような状況なら、生活保護の申請を検討する価値があります。
- 年金だけでは生活費が足りない
- 医療費の支払いが困難
- 介護サービスの自己負担が厳しい
- 家賃の支払いが苦しい
- 貯金が底をついた、または少ない
- 親族からの援助が期待できない
申請をためらう必要はありません
「生活保護を受けるのは恥ずかしい」と感じる方もいるかもしれませんが、これは国民の権利として認められた制度です。
年金と同様に、必要な方が利用すべき公的な制度なのです。
健康で文化的な最低限度の生活は、すべての国民に保障された権利です。
生活に困窮している場合は、一人で悩まず、まずは福祉事務所に相談してみることをおすすめします。
相談窓口
お住まいの地域の福祉事務所 市役所・区役所の生活保護担当課にお問い合わせください。
生活困窮者自立支援制度 生活保護の前段階として、家計相談や就労支援を受けられます。
地域包括支援センター 高齢者の総合相談窓口として、生活保護についても相談できます。
困ったときは、これらの窓口に気軽に相談してみてください。専門家が親身になってサポートしてくれます。
最後に
生活保護は、生活に困窮したすべての国民を支える重要なセーフティネットです。高齢者の方々が安心して暮らせる社会を実現するために、この制度は存在しています。
必要なときに適切に利用することは、決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、自分の権利を正しく行使し、健康で文化的な生活を送ることは、すべての国民に認められた大切な権利なのです。
この記事が、生活保護を検討されている高齢者の方々やそのご家族の参考になれば幸いです。







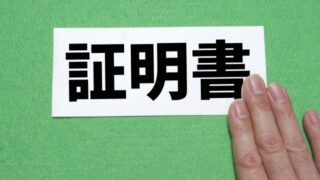







コメント