生活が苦しくなってきたから、生活保護を申請しようと考えいてるけれど、犬や猫などのペットを飼っていたら、生活保護を受けることができないのか?生活保護の申請をしたらペットを手放すように言われてしまうのか?気になるところだと思います。
結論から言うと、生活保護でもペットを飼うことは可能です。
ただし、注意点もありますので、このページでは、生活保護でもペットを飼育できる根拠とペットを飼育するうえでの各種注意点について、詳しくご紹介します。
生活保護の条件にペットは関係ない

生活保護の条件は非常にシンプルで「世帯の収入が最低生活費以下であること」です。


生活保護の条件にペットの有無は関係ないので、ペットを飼っていても生活保護を申請すること、受給すること、どちらも可能です。

もしも、生活保護の相談に行った際に相談員から「ペットを飼うだけの余裕があるなら生活保護は受けられない」と言った回答があったのであれば、それは水際作戦です。

水際作戦とは、本来は生活保護を受給する条件を満たす場合でも、申請させないようにすることです。
生活保護受給者が増えると、税金の支出も増えますし、ケースワーカーの仕事も増えることから、ペットを理由に生活保護を受けさせないようにする福祉事務所もあります。
水際作戦で何を言われても生活保護の申請さえしてしまえば福祉事務所は手順どおり審査をしなければならず、生活保護の条件にペットは一切関係ないので、兎にも角にも申請用紙を受けとり、生活保護の申請をすることが重要になります。

生活保護のためにペットを手放す必要はない

生活保護の条件にペットの有無が関係がなくても、受給開始後にケースワーカーからペットを手放すように指導されるのではないか?と心配される方もいるかもしれませんが、ケースワーカーにそんな権限はありません。

「生活保護法」
(指導及び指示)第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
上記のとおり、生活保護法で規定されているように、生活保護で指導できることは必要の最小限度しかできません。
生活保護受給者はお酒、タバコ、ギャンブルをすることも許されていますので、当然ペットを飼うことも許されています。



ケースワーカーが訪問調査に来たときに、ペットがいることがバレてしまい、「しまった!」「まずい!」みたいな顔をされる方がたまにいますが、ペットがいても、ケースワーカーは何も言いません。

さすがに多頭飼育崩壊になるような場合は生活の維持が困難なため指導しますが、普通にペットを飼っている生活保護受給者に対して福祉事務所がとやかく言うことはありません。
ペットを理由に指導をすることが出来ないため、当然、ペットを理由に生活保護の打ち切りにあうようなこともありません。

そのため、ペットを飼ったまま、生活保護を受給し続けることができます。
ペットも生活保護も、どちらも諦める必要はありません。
生活保護受給中にペットを飼い始めることもできる

生活保護受給中に新たにペットを購入したり、譲り受けたりして飼い始めることも可能です。
うつ病などの精神疾患がある場合、ペットを飼うと症状が改善されることもあることから、医師からペットを飼うことを勧められることもあるそうです。

ただし、例え医師から「ペットを飼った方が良い!」と言われたとしても、メガネ等の治療用装具とは異なり、残念ながら生活保護費からペット購入費は出ません。

そのため、新たにペットを飼いたい場合は、生活保護費をコツコツ貯金して、ペットショップで購入するか、知人から譲り受けるしか方法がありません。

ローンを組んでペットを飼うこともできるのでは?と思う方もいると思いますが、生活保護受給者は原則として借金をすることができません。

ローンが組めない理由としては、生活保護の制度上、借金が禁止されていることもありますが、ペットショップや銀行の方からしても、生活保護受給者は取り立てができないことから、ローンを組ませてくれません。
闇金業者等からは借金をすることはできますが、闇金に手を出してしまうと、最後のセーフティネットである生活保護ですら救うことができない生活を強いられることになるため、絶対に闇金業者からお金を借りてまでペットを飼おうとするのはやめましょう。

ちなみに、生活保護費だけでペットを購入するだけのお金を貯金するのは難しいため、大抵は知人からペットを譲り受けるケースが多いです。
生活保護でも飼えるペットの種類は?

生活保護受給者がペットを飼って良いことは理解いただけたと思います。
では次に、生活保護受給者が飼って良いペットに制限はあるのでしょうか?
結論から言うと、一般世帯と同様に、法律で家庭で飼って良い動物であれば、どんなペットでも飼うことができます。
ペットと言うと、犬や猫が真っ先にイメージに浮かぶと思いますが、もちろん、生活保護でも犬や猫を飼うことは当然できます。
ハムスターやうさぎ、インコ、イグアナなどについても、特に制限はないため、生活保護受給中でも飼うことができます。
私が実際に出会ったケースで言えば、金魚やメダカ、うさぎを飼っている世帯もありましたし、すごい人だとオウムを飼っている人もいました。
このように、生活保護受給中に飼えるペットの種類についても、特に制限はなく、自由にどんな動物もペットにすることが可能です。
ペットにかかる費用は全額自己負担

生活保護でもペットを飼うことは可能ですが、ペットにかかる費用は全額自己負担です。
毎月支給される生活保護費の中にペット扶助やペット加算等はありません。

そのため、ペットのエサ代、トイレ、予防接種・ワクチン代、その他体調が悪くなった時の病院代やクスリ代などペットに関するあらゆる費用は全て自己負担です。
健康であればエサ代等の月の出費は1万円~2万円くらいだと思いますので、毎月の生活保護費の中から賄うことができると思いますが、ペットがケガや病気になった場合の病院の治療費は保険が効かないため、かなり高額になります。
1回の通院・治療で数千円、手術などが必要であれば数万円も掛かるためペットを飼う場合は、それなりの覚悟も必要です。
ペットを言い訳に指導拒否はできない

生活保護受給者は自立に向けた取り組みをしなければいけません。
病気によって働くことができないのであれば、通院をして治療に専念しなければいけません。
若くて健康な人や、病気があっても軽労働が可能な場合は就職活動を行わなければいけません。
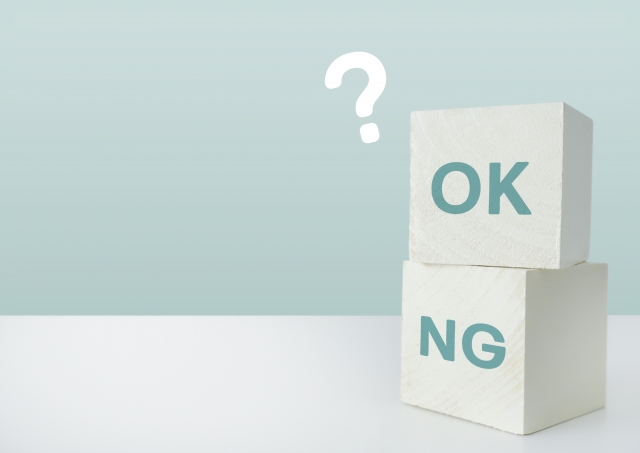
治療に専念すること、就職活動をすることは、ケースワーカーから指導指示されます。

そして、もしも指導指示に従わない場合は、最悪の場合、生活保護の廃止となります。

生活保護受給者の中には「ペットがいるから働けない」「家を留守にしている間にペットがケガをしたら、どう責任をとるのか?」と憤る方がいますが、ペットを理由に指導拒否することはできません。
一般世帯の中には一人暮らしでペットを飼いながら仕事をしている方もいるため、指導指示に従わなければ、手続きどおり生活保護の廃止となります。

大家や近隣住民とのトラブルはすべて自身で解決しなければならない
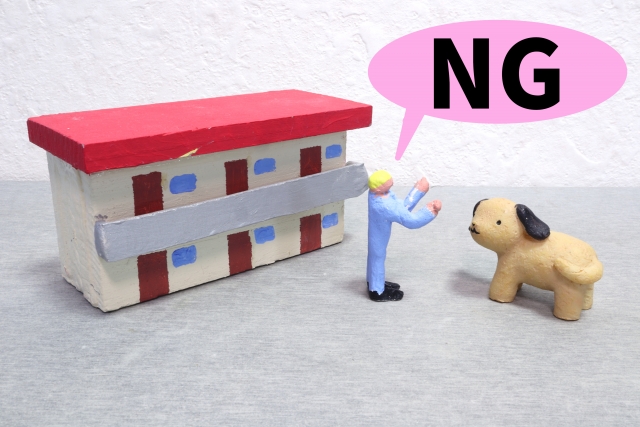
ペットを飼うと
・ペット可物件ではなかった
・騒音問題
・糞尿処理問題
・ペットがイタズラをされた
・ペットが人にケガをさせてしまった
等、様々なトラブルが大家や近隣住民との間で発生する可能性があります。
これらのトラブルに関しては、福祉事務所は一切関知しません。
生活保護受給者から相談を受けても、大家さんや隣人から相談を受けても、民民間の問題のため、福祉事務所が間に入って調整したりすることは絶対にありません。
例えば生活保護受給者がペット可物件ではないアパート・マンションに住んでいるにも関わらず、黙ってペットを飼っていた場合、大家さんが福祉事務所に怒鳴り込んで来ても何もできませんし、逆にペットが理由に生活保護受給者がアパートを追い出されたとしても、ケースワーカーは何もできません。
また、ペットが誰かを傷つけてしまったり、物を壊した場合の補償等も全て生活保護受給者自身が工面して支払わなければいけません。
このようにペットに限りませんが、トラブルが発生した場合は、全て生活保護受給者自身が自己責任で解決しなければいけないため、トラブルが起きないように気をつけましょう。
まとめ

生活保護でもペットを飼育できる根拠とペットを飼育するうえでの各種注意点について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護の条件は「世帯の収入が最低生活費以下」であることのみのため、ペットを飼っていても生活保護を受給することができる
- ケースワーカーからペットを手放すように指導指示を受けることはない
- ペットを理由に生活保護の打ち切りになることはない
- 生活保護受給開始後に新たにペットを飼い始めることもできる
- 飼えるペットの種類に制限はない
- エサ代や病院代など、ペットに掛かる費用は、すべて自己負担しなければならない
- 通院指導、就労指導等はペットを理由に断ることはできないため、必ず指導指示に従わなければいけない
- ペットが人に怪我させた場合や物を壊した場合など、トラブルが発生した場合も全て自己責任で解決しなければならない
となります。
生活保護でもペットは飼えますが、ペットに掛かる費用は全額自己負担であること、ペット関連のトラブルが発生した場合も全て自己責任であること、この点だけは特に注意してください。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/















コメント