「生活保護って誰でも受けられるの?」
「収入が少ないけれど、条件に当てはまるのか知りたい」
「扶養してくれる家族がいないか聞かれたらどうなる?」
生活保護制度は「最後のセーフティネット」であり、一定の条件を満たせば誰でも申請できる権利があります。
しかし誤解も多く、ネット上でも間違った情報が多いため、正しい条件を理解していない人が非常に多いのが現状です。
この記事では、元ケースワーカーの視点から、生活保護を受けるための条件・審査のポイント・申請が通らない理由まで、疑問をすべて解決する形でわかりやすく解説します。

生活保護を受けられる4つの主な条件

生活保護が適用されるための条件は、大きく次の4つです。
- ①資産がない(または生活費に充てられる資産が少ない)
- ②働けるけれど収入が最低生活費に満たない
- ③働けない(病気・障害・高齢など)ため生活ができない
- ④扶養義務者から現実的に援助が受けられない
それぞれ詳しく説明します。
①資産がない:生活費に充てられる資産が条件を満たしていない
生活保護では、まず「資産」から確認されます。
資産とは、生活費に転換できる財産のことです。
チェックされる主な資産は
- 預貯金
- 車・バイク
- 土地・建物
- 保険の解約返戻金
- 貴金属
- ブランド品・高額家電
生活費に充てられる資産を先に使うことが前提となっているため、「お金もあるけど生活保護も欲しい」という考えでは受けられません。
ただし例外も多く、次のような場合は資産があっても認められるケースがあります。
- 車が生活必需品(地方で通勤や通院に不可欠など)
- 持ち家に住んでおり、売却困難な場合
- 預金があっても、医療費や家賃滞納に充てた結果残っていない場合
ケースワーカーは画一的に判断せず、「その人の生活にとって必要かどうか」で評価します。
②働いているが収入が最低生活費に満たない
生活保護では毎月、国が定める「最低生活費」という基準があります。

これは地域ごとに異なり、東京と地方では数万円単位で差があります。
例えば単身世帯のケースでは、
生活費(生活扶助)+家賃の基準額(住宅扶助)= その地域の最低生活費
となります。
仮に最低生活費12万円の地域に住んでいる場合、世帯収入が8万円であれば、最低生活費に4万円足りていないため、この足りていない4万円分について生活保護が支給されます。
このように働いていても、収入が基準を下回る人は生活保護の対象になります。

特に増えているのは以下のケースです。
- 非正規雇用もしくはアルバイトのため収入が不安定
- 病気のため勤務時間を減らしている
- シングルマザーで収入が低い
- 高齢で働ける範囲が限られている
生活保護は「働いていると受けられない」という誤解が多いですが、働きながら生活保護を受けている人はたくさんいます。

③働けない事情がある(病気・障害・高齢など)
生活保護を受ける重要な条件のひとつが「労働能力」です。
働けるのか、働けないのか、働けてもどの程度なのかを判断されます。
働けないと認められる主な理由
- うつ病・統合失調症などの精神疾患
- 心臓病・腎臓病などの慢性疾患
- 怪我・疾病で長期療養中
- 重度の障害がある
- 高齢(一般的には65歳以上)
- 介護が必要
- 子育て中(特にシングルで未就園児がいる場合)
医師の診断書や障害者手帳が必須ではありませんが、客観的な資料があるとスムーズに認められやすくなります。
ない場合もケースワーカーが病状調査を行い、就労の可否を判断します。

④扶養義務者から現実的な援助が受けられない
生活保護申請時には 扶養義務者(親・子・兄弟)への扶養照会が行われます。

よく誤解されていますが、扶養照会があっても必ず援助しなければいけないわけではありません。
援助できない場合は、調査に対して「援助できない」と回答すれば、それで生活保護の審査は進みます。

例えば、
- 疎遠・絶縁状態
- 家庭事情で援助できない
- 経済的に苦しい
- DVなどの危険がある
こうした理由で援助ができない場合、生活保護の審査に影響はありません。
最近では、厚労省が扶養照会を“柔軟に”扱うことを指示しており、 以前よりも保護が受けやすい制度になっています。
生活保護が受けられないことが多いケース

条件に当てはまらない場合、生活保護は認められません。
よくある不支給事例は次の通りです。
①働けるのに働く意思がまったくない
生活保護には「自立の助長」という原則があります。
働けるのに働く意思がない場合は非常に通りにくくなります。
ただし、
- 精神疾患
- 障害者
- 持病がある
- 子育て中
などの背景がある場合は柔軟に判断されます。
②高額な資産を隠し持っている
- 多額の預金
- 自動車
- 不動産
- 株や投資信託
- 生命保険・学資保険
- ブランド物や宝飾品
これらがある場合は、まず生活費に充てることが求められます。
③生活実態が不透明
- 住んでいる場所を教えない
- 家を訪問しても不在が続く
- 誰と住んでいるか不明
こうしたケースでは、生活実態が確認できず最悪の場合生活保護の却下・廃止になります。

④親族の援助が十分に受けられる場合
例えば
- 親族からの十分な仕送りがある
- 同居家族に十分な収入がある
などの場合、保護が不要と判断されます。
生活保護の審査でチェックされる「6つの重要ポイント」
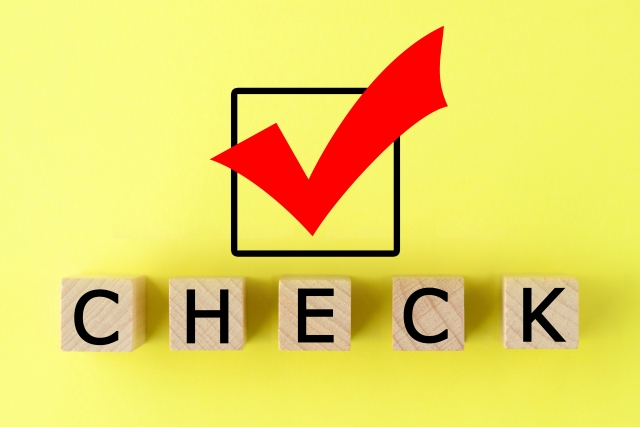
生活保護の審査は、次の6つの要素を総合的に見て判断されます。
① 現在の収入
給与・年金・手当・仕送りなど、あらゆる収入すべて。
② 資産の状況
預金・車・不動産・株・投資信託・保険など現金化できるものすべて。
③健康状態・就労能力
医師の診断書や通院状況、就労状況。
④ 住居の状況
住居の・家賃・共益費等、住居に掛かっている費用すべて。
なお、家賃・共益費が高すぎる場合は引越しをするように指導されます。

⑤扶養義務者からの援助の可否
扶養義務者に対して調査します。
援助できる場合は審査に影響しますが、援助できない場合は審査に何も影響はありません。
⑥生活実態の確認(訪問調査)
生活保護法28条に基づき、ケースワーカーの生活状況等、立入調査が行われます。

生活保護を受けるために必要な書類

申請時に必要なのは主に以下の書類です。
- 本人確認書類(免許証、保険証など)
- 預金通帳(過去3〜6か月分)
- 家賃の契約書
- 給与明細・源泉徴収票
- 病院の診断書(必要に応じて)
- マイナンバーカード
- 印鑑
ただし、揃っていなくても申請は可能です。
必要な書類がない場合はケースワーカーが協力してくれます。
生活保護の申請から決定までの流れ

1.申請
生活保護は福祉事務所で「生活保護を申請します」と伝えるだけで申請できます。
2.面談
ケースワーカーが収入・健康・生活状況を確認します。
3.訪問調査(生活保護法28条)
ケースワーカーが自宅を訪問します。
4.必要書類の提出
預金通帳や家賃情報などのコピーを提出します。
5.審査
生活保護の審査は原則14日、最長30日以内に決定します。
6.支給開始
生活保護が認定されれば翌月から支給されます。
なお、支給金額については申請日に遡って支給されまうs.

まとめ|生活保護は条件を満たせば誰でも利用できる制度

生活保護は「甘え」「恥ずかしい」と言われがちですが、本来はどんな人でも困ったときに利用できる権利です。
この記事のポイントをまとめます。
- 生活保護の条件は4つ(資産・収入・就労能力・扶養)
- 働きながら受給している人も多い
- 病気・障害・高齢の場合は保護対象になりやすい
- 扶養照会があっても援助は強制されない
- 資産を隠すと不正受給になる
- 申請は誰でも可能で拒否されない
生活が苦しいなら、迷う必要はありません。
生活保護は「あなたの命と生活を守るための制度」です。







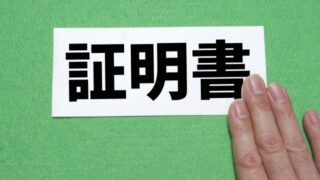





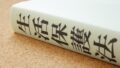

コメント